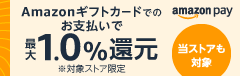職人の世界に飛び込んだ人たち
情熱を無駄にするのはもったいない 若き江戸切子職人・坂本優輝が見据える職人の未来
|
|

江戸切子の魅力は、その圧倒的な“美しさ”にある。あらゆる角度から差し込まれる光が反射し、繊細な模様を写し出だす。その儚い美しさに、不思議と惹き込まれてしまうのだ。 今回は、堀口切子に所属する江戸切子職人・坂本優輝さんにインタビュー。高校生で切子職人を目指した背景と、伝統を受け継ぐことに対しての想いを聞いた。
190年の歴史を持つ伝統工芸
 「籠目ニ菊繋文切立盃(かごめ に きくつなぎもん きったてはい)」 そもそも、“江戸切子”とはなんなのだろうか。坂本さんに、江戸切子という伝統工芸について教えてもらった。「江戸切子というのは、ガラスの表面を削ったり磨いたりと加工を施したガラス製品のことを言います。始まりは1834年、江戸の日本橋大伝馬町。加賀屋久兵衛(かがやきゅうべえ)という方が製作したのが始まりと言われています」 およそ190年の歴史がある伝統工芸、江戸切子。きっと当時、江戸切子を始めてみた人も筆者と同じくその美しさに目を奪われたことだろう。 そして坂本さんは、江戸切子に4つの定義があることを説明してくれた。「1つ目はガラスであること。2つ目は、手作業で加工をしていること。3つ目は、主に回転道具を使用していること。4つ目は、東京都近郊で作られていることです」 江戸切子と聞くとグラスに模様が彫られているイメージもあるが、いまの条件を聞く限りガラスであればほかにも作品の幅はありそうだ。「江戸切子はグラス以外にも、ぐい呑、照明の器具、トロフィーなどにも使われていて、柔軟で自由度の高い工芸なんです」 
とはいえ、どうやって手作業でここまで細かい模様を入れているのだろうか。坂本さんに、江戸切子の大まかな製作工程について教えてもらった。「まず最初に行うのが、“割り出し”という作業です。これは、カットの基準線を引く工程になります」 
坂本さんが修行を始めて最初に覚えたのも、この“割り出し”だという。「江戸切子の作業にはやり直しが効くものと効かないものがあるんですけど、割り出しは基本的にやり直せる作業になります。と言ってもこの割り出しには、江戸切子のノウハウが詰まっている大事な工程なんです。最初の基準になるので、そこがブレてしまったら元も子もないんですよ」 割り出しは、最初に書く設計図のようなものだろう。「割り出しでは必要最低限の縦と横の線だけを引いていきます。よく細かいカットの斜めの線も引くのですか?と聞かれますが、割り出しの線が増えると、割り出しにかかる時間も多くなり、カットをする際に分かりづらくなってしまうので基本的には引きません」 

江戸切子の設計図を見せながら、坂本さんは割り出しからどのように工程を重ねていくのかについて解説してくれた。「割り出しが終わったら、次は“粗摺り”という工程になります。粗摺りでは、まずはざっくりと模様を削っていきます。そのあと“三番掛け”という工程で、粗摺りの部分より細かくなめらかにカットを施します」 
「粗摺りと三番掛けには、ダイヤモンドホイールという工具を使うんです」そう言いながら坂本さんが見せてくれたのは、棚一面に収納されたダイヤモンドホイールの数々だ。作品に合わせて、使用するダイヤモンドホイールの粗さや幅が違うようだ。削る技術はもちろんだが、これだけある道具の見極めも、作品の出来栄えにかなり影響してきそうだ。 
ダイヤモンドホイールは、人工のダイヤモンドが埋め込まれている工具で、よくみると表面がキラキラしている。この工具を駆使して細かい模様が削りだされているということはわかるが、それにしてもあそこまでの細かさを出せるのはやはり不思議だ。 「三番掛けは目の細かいダイヤモンドホイールを使うのですが、目が細かいということは研削力としては落ちるわけです。削る労力を減らすためにも、最初に粗摺りでざっくり削る必要があります。その一方で、細かい文様を入れる箇所は粗摺りを通す必要がないので三番掛けのみで行うこともあります。製作工程として、すべての工程を必ず通らなければいけないわけではなくて、必要に応じて工程や道具を選択していきます」 
“ガラスを削る”という行為はあと戻りができない。もしズレてしまったり、間違えて削ってしまったらどうするのだろうか。「自分も結構そそっかしいタイプなんで…(笑)。当て間違えないように気をつけてはいますが、たとえば黒いガラスを取り扱うときは光を通してくれずダイヤモンドホイールが当たるところが見えにくいので、最初当てたときに基準線から少しズレてしまうということはありますね。でも、最終的に削る幅というのがあるので、削りながらその範囲内に収まるように調整していきます」 
そう解説し、坂本さんは目の前で削る様子を見せてくれた。筆者の体感だが、数秒のあいだにカットされている部分が増えており、「いま削ってましたか?」と心のなかで確認してしまうほどあっという間に、坂本さんは綺麗な模様を削っていた。坂本さんは27歳という若さながらも、職人歴は9年目になる。何気なく見せたプロの腕に思わず圧倒されてしまった。 そんな坂本さんが、覚えるのに1番苦労した工程は“磨き”だという。「磨きは三番掛けや石掛けのあとに行う工程です。樹脂製のパッドに研磨剤をつけて、削ったところをなぞるように磨いていきます」 
「綺麗に磨くには、親方や先輩の削った通りに手を動かさないといけないのですが、上手く磨けないと“磨き残し”といって、白っぽく残ってしまう部分が出てくるんです。当時はその磨き残しが出ないように磨こうと思ってもなかなか上手くできませんでした。その品物については納品日があったため、できるだけ早く仕上げようと思ってもなかなか仕上がらず、先輩の手を煩わせてしまったこともしばしばありました。今ではだいぶ習得しつつあるとは思いますが、まだ高みには至っていないなと思います(笑)」 9年目にしても「至っていない」と語る坂本さん。改めて、職人の技術にゴールはないことを感じた。以前の取材でも感じたが、どんな職人さんもずっと理想のクオリティを追い求め続けている。ものづくりに正解はない。だからこそ、理想を追い求める情熱がどれだけあるのかが試されるのだと感じた。
「情熱を無駄にしちゃうのはもったいない」

坂本さんが切子の世界を知ったのは、高校生のころだったという。「昔から流木を拾って木刀を作ったり、石を削って勾玉を作ったり、ものづくりが好きだったんです。あとは、色のついたビー玉とか宝石とか、キラキラしているものも好きでした。高校2年生の夏休みのときに、テレビで江戸切子の特集をたまたま見て。『すごく綺麗だな』って思ったんです」 「それからインターネットで江戸切子のことを調べていたら、『堀口切子』のことを見つけたんです。親方の作品や、『黒被万華様切立盃(くろぎせ まんげよう きったてはい)』を見て、“こんな素敵なものを作る職人になりたい”と思いました」  「黒被万華様切立盃(くろぎせ まんげよう きったてはい)」 坂本さんは当時、進学と就職でちょうど迷っていた時期でもあったという。そんな偶然のタイミングで切子と出会ったことも、大きかったのかもしれない。「先生に相談したら、『インターンをやってみたらいいんじゃないか』と言われたんです。でもインターンを募集している工房なんてそうそうないし、そもそも自分自身『インターンって何?』っていう感じでした。そしたら先生が話をつけてくれて、1週間インターンに行けることになったんです」 だが、告げられた行き先は『株式会社堀口硝子』だったという。「『株式会社堀口硝子』は、親方のお父さまの会社なんです。だから、あれ?と思ったんですけど、行ってみたらすごく歓迎してくれて江戸切子の作り方や歴史など色んな事を勉強させてもらいました。そのインターンの最終日にたまたま親方が堀口硝子の工場にいらっしゃって。堀口切子の工場を見せてくれることになったんです」 念願の『堀口切子』。坂本さんは、代表である三代秀石・堀口徹氏に、切子への思いを伝えたようだ。「あの1日がなかったら、ここに就職できていなかったと思っています(笑)。自分は本当に運が良かったんです」 
「いまは親方含め6人が働いているのですが、そのときは親方と先輩の2人でやっていて、ちょうどもうひとり欲しいなっていうタイミングだったようです。いまでも思うんですけど、この業界は入りたいと思って入れる業界じゃないというか。応募する人にとっても一期一会の出会いかもしれないですけど、その前に会社側が受け入れられる状況じゃなかったり、雇用するにしても体制が整っているかいないかなどもあると思います。つくづく、自分は運が良かったです(笑)」 そう笑顔で話す坂本さん。たしかに人生の出会いやきっかけは巡り合わせというものがあると筆者も思うが、本当にそれだけだろうかと、坂本さんの話を聞きながら思っていた。進路に迷っているタイミングで江戸切子を知ったことや、親方さんとの出会いはたしかに偶然かもしれないが、最初に「これを作る職人になりたい」という坂本さんの思いと行動がなければすべてはなかったことなのではないだろうか。 坂本さんは北海道出身だ。高校2年生の17歳、インターンとはいえ東京の職人の仕事場にやってくる行動力と勇気が、果たして自分が17歳のころにあっただろうか。 
当時の決断について振り返りながら、改めて職人に必要だと思うことについて坂本さんに聞いてみた。「『思い立ったが吉日』という言葉がすごくいいなと思っていて。何をするにも、やりたいなって思ったときが1番情熱に溢れているじゃないですか。それを先延ばしにしてしまったら、ちょっと自分のなかでサボる気持ちが出てきてしまうような気がして」 「やりたいって思ったんだったら、やってみればいいんじゃないって思います。これは職人の道を目指すことに限った話ではないかもしれないんですけど、そのときの熱量ってやっぱり自分がやりたいからだし、その情熱を無駄にしちゃうのはもったいない。自分みたいに運よく受け入れてくれるところがあるかは別なんですけど、人生1度きりのなかで、『やりたいな』って思ったことを、思ったときに行動に移すっていうのがすごく大事なんじゃないかなと今になって思います。もしそれが失敗に終わっちゃったとしても、その気になったら意外とどうとでもなるんじゃないかと思うので(笑)。いまを大事に生きることが大切なのかなと思います」
自分たちの生きる時間は、これからの伝統になる

職人として初めて手がけた商品は、『よろけ縞』だと坂本さんは振り返った。「縦線を連続で入れていくデザインなんですけど、このよろけ具合だったり、どれぐらい節をつけるかとか。シンプルに見えてすごく難しいんです。当時は、使っていないグラスを数十個ほど練習で使わせてもらってから、本番に臨みました。すごく緊張したのをいまでも覚えています」 「いまは当たり前のように、削って磨いて出荷をしていますけど、自分が手がけた商品が日本や世界の各地に届いて、誰かのもとで使われている。改めて考えるとそれってすごく嬉しく思う一方、『江戸切子』を作る一員としての責任感もあって、とても不思議な感覚です」 
堀口切子では、江戸切子を使ったジュエリーの制作も行っているという。伝統工芸でありながらも、新しいスタイルなどに挑戦し、日々作品も進化しているようだ。 「江戸切子の190年という歴史のなかで、変わっていない部分というのが伝統の本質だと思うんです。ガラスを削って磨くことだったり、誰かの手に渡ったとき、見てもらったときに『うわ、これすごいね』『綺麗だね』って驚かせたり、感動させることだったり。それが江戸切子の本質なんだと思います。堀口切子はその本質をすごく大切にしていますし、しっかりと踏襲していると思います」 坂本さんは、江戸切子という技術に対して語りながらも、こう続けた。「いまこの瞬間、自分が江戸切子職人として活動できる期間のなかで、精一杯できることだったり、務めなければいけない役目を大事にしながら、新しい自分なりの作品を作っていきたいと思っています」 坂本さんは、2023年の『第35回江戸切子新作展』で東京都産業労働局長賞を受賞(「RINKA」)。2024年の『第36回江戸切子新作展』で江東区議会議長賞を受賞している。2024年の作品「心祈万海(しんきばんかい)」は、刀を模した作品を制作した。 「この作品は自分のなかでも、けっこう象徴的な出来事だったかなと思っていて。江戸切子新作展で出品されている作品は大皿や鉢、花瓶などの形状のものが多いのですが、なんか…目新しくてかっこいいものを作りたいなって思って」 筆者も「心祈万海(しんきばんかい)」を最初に見たときは、「これも江戸切子なのか」と驚いた。これこそ、先ほど坂本さんが語っていた、“本質を踏襲しつつ新しいものを生み出す”ということなのではないだろうか。 「これからはいままでやってきていることを大事にしながらも、誰も見たことのないような作品だったり、人を驚かせて『すごい!』と感動してもらえるようなものを作っていきたいです」  「心祈万海(しんきばんかい)」 伝統的なものは、どうしても“変えてはいけない”という思いにとらわれがちだ。もちろん、変わらないからこそかっこよく、そこに愛が込められているという部分もある。だが、存在を残していくためには、次の世代が柔軟に新しいかたちへと変えながらも受け継いでいくこともまた、大切なことなのではないだろうか。 坂本さんの「本質を踏襲しながら新しいものを作る」という思いは、江戸切子に限らずすべての歴史、伝統、文化において言えることなのかもしれない。そのためには、まず本質とはなんなのかを見極めることが必要となる。 自分がいま触れている文化、日々行っている仕事、人とのつながりの“本質”はなんなのか。そのうえで、自分はどう行動していくべきなのか。今回は、江戸切子職人・坂本さんから大事な考え方を教わったような気がした。 |
|
- 2025.05.20
- 10:18
職人の世界に飛び込んだ人たち一覧
|
職人になるとはどういうことなのか?? 未知の世界、だからこそ興味がある。 ここでは当店で商品・作品のお取り扱いの有無に関わらず、取材を通して、魅力ある職人さんの職人になった経緯やその前後にあるストーリー、仕事の魅力や苦労をお伝えしたいと思います。 良いことばかりではなく、大変なことや想像を超えるような苦労もあるはずです。それを様々な角度からお伝えします。綺麗事ではなくリアルな「職人になる」ということを伝えたいと思ってます。 ありのままをお伝えして、感じていただける魅力は必ずありますし、そこに本当の魅力があるはず。 そして、ここでの紹介を見て職人目指してみようと考える方が増えれば何よりです。 |
|
職人No.1 指物師・益田大祐 「時間を超えて側にいてくれる“指物”の世界とは。指物師・益田大祐氏が語る職人の魅力と覚悟」 
|
時間を超えて側にいてくれる“指物”の世界とは。指物師・益田大祐氏が語る職人の魅力と覚悟
|
|

金釘を使わずに、木と木の組み合わせだけで家具や調度品を作り上げる技術“指物”。指物には1000年以上の歴史があると言われており、日本を代表する伝統工芸のひとつだ。 今回は、墨田区で『指物益田』を構える指物師・益田大祐氏をインタビュー。指物師を目指したきっかけや、職人という世界のリアルについて語ってもらった。
指物が何度も蘇るワケ

安価で組み立ても簡単な家具やインテリアブランドが増え続けている現代で、指物を所有している人はどのくらいいるのだろうか。指物師である益田大祐さんに、指物とはそもそもどういった技術なのかについて教えてもらった。 「指物とは、金釘を使わずに作る家具屋調度品のことを言います。穴を掘って、“オス”と“メス”を作って、組み合わせる。いまは“膠(にかわ)”や木工ボンドなども使うのですが、昔はご飯粒を潰してノリ代わりにする“続飯(そくい)”という方法もありました」 「指物は、修理をして何年も使い続けられることを前提としています。だから、使う接着剤もお湯で洗って取れる程度のものしか使いません。組み合わせを作って嵌めて、弱めの接着剤を使って締める。水分を含むと木が膨らむ原理も利用して、強度を高めます」 最終的に指物は、木の組み合わせだけで成り立つということだ。実際に益田さんに見せてもらった組み合わせは、少しの隙間もなくぴったりと“オス”と“メス”が密着して、ひとつのかたちになった。 
「指物はなんというか、数学的なんですよね。組み合わせる基本の型があって、作るものに合わせて応用して型を変えていくんです。必要であれば、複雑化させる。組み合わせる部分の表面積を増やすほど頑丈になります。でも木を削れば削るほど木の強度は落ちるので、そこはバランスを取る必要があります」 組み合わせの型は“仕口(しくち)”といい、木の体積も考えながら設計をする。大きな作品になればそれだけ複雑になるということだ。正確に彫ったり削ったりするだけでも驚きだったが、改めて指物の難しさと技の凄さを感じる。 
益田さんは、普段の依頼を振り返ってこう語った。 「1度作ったら何十年も使うことができるので、江戸時代に作られた指物の修理依頼なんかもよく来ます。あとは祖父の代から使っている鏡台を直して欲しい、といった依頼なども来たりしますね。ちゃんとした技術で作られているものであれば、長い年月が経っていても新品同様に直すことができるんですよ」 江戸時代のものを、令和に修理することが可能なのが驚きだ。指物の技術は、指物師がいる限り、想像しているもっと先の未来までつなげることができるのだろう。 
1000年以上の歴史があると言われている指物。益田さんに、その始まりについて教えてもらった。 「指物の源流は京都になります。いまのように実用的なものというよりかは、自身の権力や身分を示すものを作ることが多かったようです。刀置きとか、嫁入り道具とかですね。それから江戸時代になり、商人が権力を持つようになってから、徐々に指物で商売道具も作るようになり、指物はより民衆的な文化になりました。地方では土地に余裕があるので大きな箪笥が作られたり、狭くて火事が起きやすい江戸では、小ぶりでコンパクトなものが作られたり、同じ指物でも地域によっても違いが出てきたのもこのくらいからですね」 薬の行商人なども、指物を使っていたようだ。指物でできた薬箱を組み立て、売り物を詰め、背中に背負い、「エッホ、エッホ」と運ぶ当時の商人の姿が目に浮かぶ。指物の歴史は、その土地で暮らす人たちの生活が透けて見えるようでとても面白い。そのくらい、指物は人々の生活に根付いた技術なのだろう。 
「道具も発達し、扱える材料も増えてきたので、職人同士も技術を競い合うようになり、指物はどんどん進化していきました。また、歌舞伎が流行したのも江戸時代です。小道具や鏡台が必要になるので、さらに指物の需要も高まりました。雅(みやび)なものを作るところから、街に暮らす人が使うものを作る技術へと、立ち位置が変わっていったんです」 昔は、職人と依頼主のあいだに”問屋”という存在があったという。いまのように、職人が直接お客さんと関わるというわけではなかったようだ。 「問屋は、いまでいう仲介業者のようなものですね。太い問屋についた職人はそれだけでもう忙しく、ほかから注文を受けるのも難しいから、歌舞伎専門、お茶道具専門など、自ずと自分の得意な分野に特化していったんです。でもいまはそれだけだと食べていけないので、何個か分野を担当しています。うちも歌舞伎関係、茶道具、香道具など幅広く制作しています」
デザインの面白さを求めて

そもそもなぜ、益田さんは指物師になったのだろうか。そのきっかけについて聞いた。 「私は最初、高等専門学校の工業デザイン課に通っていました。学生時代からなんとなく『デザイナーになりたい』と思っていて。その後、家具の製造会社に入社したのですが、ちょうどバブル崩壊のときだったんです」 「もうそんな時代のデザイン部なんて、1番人員を必要としていないじゃないですか(笑)。自分がそこにいる意味がわからなくなっていた時期というのもあり、じゃあ自分で技術を身につけてデザインができるようになればいいと思ったんです」 軽快に笑う益田さん。世のなかの景気に追い詰められるわけではなく、そこから柔軟に進路を選んでいった姿に、職人としての根幹を感じる。 益田さんが指物師になったのは、世のなかの流れだけではなかったようだ。 「現場を見ると大量生産をするために工作機械を使っていて、本当に自分の手で技術を身につけているのは年配の方たちだけ。だから、機械を使って作れるものに限界があるんじゃないかと思ったんです。もしそうなら、デザインって面白くないかもと感じました。まだ就職して1年目だったんですけどね(笑)。技術を習得しているのもこの年配の方たちが最後の世代かもしれない、ということもうっすらと感じていて」 「職人になったのも、『伝統工芸を守りたい』というよりかは、自分のデザインの幅を広げるというのが大きな理由でした。あとは、現状をどうにかしたかったタイミングというのもあります。ちょうどそのとき雑誌に親方が載っていて、お話をお伺いしに行きました」 職人の道を選ぶとなると、かなりの覚悟と決断があるというイメージがあったが、益田さんの選択は想像以上に軽やかで、職人という世界を“そんなに怖がらなくていいよ”と背中を押してくれるようなものだった。 
そんな益田さんが門を叩いた職人の世界は、どんなところだったのだろうか。 「私が弟子入りしたのは、お父さんと息子さんがやっているところでした。息子さんが私に仕事を教えてくれたので、側から見ると兄弟子が親方という感じでしたね。お父さんは温厚で物静かな方でした。息子さんはザ・下町のお兄ちゃんという感じです。三社祭が近くなるといなくなるような(笑)。組合には私のほかに7人ほどお弟子さんがいたのですが、みんな辞めてしまいましたね」 益田さんは、当時についてゆっくりと振り返った。 「そうですね……30歳前後になると、『これで食っていけるのか』とやはり現実的に考え始めるんです。家具屋さんに就職したり、教員免許を持っている人は教師になったり、それぞれの道に進んでいきました。やっぱりその年代って、普通に働いている同級生はそれなりに年次を重ねて、しっかりとした生活を送り始める歳でもあります。今後の人生設計を考え、続けるのは難しいと判断する人が多かったのかもしれないですね」 職人の世界は、飛び込むだけが決断ではない。挑戦したその先に、改めて『自分の人生はこれでいいのか』という自分自身との戦いや葛藤が待っている。 「京都などでは会社として指物師が働いているところもあるし、親方さんのもとに職人さんが5、6人いるっていうのが当たり前なのですが、東京は場所が狭いこともあって大きくやるのがなかなか難しいのもあるのかもしれません」 
そんな人生の壁を、益田さんはどうやって乗り越えたのだろうか。当時のリアルな暮らしぶりについても教えてもらった。 「実家が都内だったので、最低限の暮らしは確保できていたんです。それでも同世代の一般的な給料よりかは安かったので、土日は学生時代にアルバイトしていたラーメン屋さんにお世話になったりもしていました」 そんな修行時代を乗り越え、益田さんは30歳のときに独立を果たしたという。改めて修行時代を振り返って、1番苦労したことについても聞いてみた。 「道具ですね。どんな仕事もそうだと思うんですけど、自分が思った通りに道具を扱えるようになるまでが難しかったです。それに指物師が扱うのは刃物なので、毎日何十回も研がなければいけません。若いときはそればっかりに時間が取られてしまって、「仕事しろよ」となっていました(笑)。刃物も人が打って作ったものなので、調子も一定というわけではなく、いいときと悪いときがあるんです。そういうときにどうするのかという、道具との付き合い方がわかるようになるのも時間がかかりましたね」 

どんな仕事でもそうだろう。筆者もいまでこそMacBookを平気な顔をして使っているが、スムーズに仕事を進められるようになるまでに、拡張機能やらショートカットキーを覚えなければいけなかった。 「あとは材料の見極めですね。指物は天然木を使っています。現在は人工的に圧力をかけて、木の水分を抜いて乾燥させる技術もありますが、指物に使う材料でそれをしてしまうと割れたりしてしまうので、銘木屋さんでは乾燥させるために何十年もかけて、ときには店主さんのさらに上の世代のときから置いてあったりします。指物では、そうして自然の力で乾燥させた天然木を使うんです」 筆者が今回の取材でもっとも驚いたのが、この話だ。何十年もかけて乾燥させた貴重な木材なんて絶対に失敗が許されない。少し想像しただけで緊張で動悸が激しくなるようだった。 「購入するときは、必要な厚さの1.5倍ほどの厚さに製材します。なぜかというと、いままで空気に触れていなかった部分が露出すると、木が動くからなんです」 木が“動く”? まるで動物の話をしているようだと感じた。どういうことなのか、初心者の筆者に向けて、益田さんは丁寧に説明してくれた。 「かたちが捻れたりして、変化するんです。だから、工房に持って帰ってきて重しを乗せて、目的の厚さになるまで1年ほど平積みをすることもあります」 ここでまた衝撃を受ける。購入してからさらに1年ものあいだ工房に置くとは。指物のスケール感にふたたび圧倒された。 「一気に削って薄くすると、また木が動いて狂ってしまうので、1か月で1ミリくらいの間隔でだんだんと薄くしていくんです」 
1か月で1ミリ。こんな世界があったとは。そんな工程を経て生まれた指物は、自分が想像している以上に職人さんがかけた時間や愛情、こだわりが詰まっていることを知った。 「そこが指物に魅了されたひとつでもあるんですけどね。木によっては、育ってきた環境で癖があります。たとえば山の斜面で育った木は、自分の重さに耐えるように育っています。そういった木を伐採すると、もう負荷がないのに何年も反発するようにしなるんです。そういう木はベッドの板に使ったり、木それぞれの特性も考えながら作っていますね」 なんだか人間の話をしているみたいだ。私たちと同じように、木にも生い立ちや性格がある。きっと指物師にはわかるのだろう。この子たちがどんな人生を歩んできたのか。
作るだけが職人ではない

益田さんに、改めて職人に必要な要素とは何かを聞いた。「そうですね……。人と話すのが苦手で、ものを作っている方が向いているという理由で職人を目指す方がよくいるんです。でもそれでは職人になるのは無理ですね」筆者も職人に対して、寡黙に手を動かす印象を持っていた。 「それは昔の話で。それこそ問屋さんがあったから、職人は仕事場にいて発注を受けたらよかったのですが、いまはその問屋さんもないし、黙って作っていれば売れるという時代でもありません。材料の値段もあってないものなので、交渉も必要になります」 職人と依頼主をつなぐ問屋という存在。それがなくなったいま、どうやら現代の職人は作る以外の部分も担う必要があるようだ。 「売り場も減ってきていますからね。少し前までは百貨店の催事売り場などで販売することもあったのですが、いまは物産展など食品の勢いがすごいので。そうしてコツコツ真面目に技術を身につければ食べていける保証はない。だからこそ、じゃあどうするのかを考える力が必要になると思います。その先を考えないといけない時代ですよね」 「まあ、自分たちもこの先どうなるかわからないので(笑)。だからこそ、若い世代には+αでほかの技術を習得して掛け合わせたり、職人という固定概念にとらわれずに、幅広い目線でものづくりを考えていくことも大事なのかなと思います」昔のやり方や技術を受け継ぐことはもちろん大事なことだ。だが、現実問題それだけで生活が成り立つ時代ではなくなってきていることを、益田さんの話から感じた。 だが、いまの時代だからこそ使える技術や需要が生まれたのも事実だろう。実際に益田さんが新たに取り組んでいる事例について教えてもらった。 「スーツケース茶室『ZEN-An禅庵』というプロジェクトに、指物師として参加しました。日本でも茶室を作る人は少なくなっていて、海外の販路を開拓する狙いもあって、スーツケースに入る茶室というのを制作しました。お線香が消える15分間で組み立てることができるという、少しパフォーマンス的な部分も含めて発表させていただいたんです」 [動画]世界中どこでも持ち運びできる茶室!スーツケース茶室「ZEN-An禅庵」 「そのスーツケース茶室も、結果海外からの反響が多く、販売もほぼ海外の方です。お客さんもそうですが、職人側でもいまは海外の勢いがすごいですね。弟子入り志願やインターンも外国の方がほとんどです。このあいだも、ドイツの大学で木工を学んでいる方が、日本の指物を教えて欲しいとインターン志望でいらっしゃいました」 インバウンドで外国からの観光客や労働者が増えていることは知っていたが、まさか職人を目指す外国人も増えているとは。日本の文化も、時代とともに変化の波が訪れている。 そして益田さんは、職人の動きが時代によって変化したことについてこう振り返った。 「私は作る技術ももちろん大事なのですが、人と人とのつながりも同じくらい大事だなと思っています。問屋という存在がなくなって、お客さんと直接お話しする機会もかなり増えました。たとえば歌舞伎の業界の方なんかはお忙しいので、ネットで調べるより口コミでお仕事をいただくことも多いんですよ。ネットは情報がありすぎるので、どこに頼むべきなのか逆にわからない。だから、特殊な分野の方ほど口コミで決める傾向が強いんです。そういう意味では、時代に逆行している部分もあるかもしれません(笑)」 インターネットが定着したからこそ、強くなる“口コミ”の力。一見便利な世のなかになったようにも感じたが、同時に情報の取捨選択に労力を割かなくてはいけなくなったのも事実だ。そして、機械ではなく、職人の手や血が通った指物の魅力は人を介して知る方が、魅力や価値が伝わるような気もした。 「非効率と言えば非効率ですけれど、でもそうやって長く付き合いが続くことはいいことですし、指物は1度買えば終わりというわけではないので。そういった先の時代に続いていくつながりも、指物に求められているところなのかなと思っています」 
修理ができることを前提として作られた“指物”という存在。ただ長く使い続けることができるだけではなく、多くの人の手に触れられてきた歴史や時間の積み重ね、使う人と一緒に同じだけの時間を過ごしてきた木の人生を感じることができる。 指物は、場所を変え時間を超え、ずっととなりにいてくれる存在だ。流行や時代が目まぐるしく変わる現代だからこそ、人生をともにする安心感を与えてくれるだろう。指物師がいる限り、指物は生き続けられる。そんな人とモノの枠を超えた、不思議なつながりを教えてくれた。 |
|
- 2025.05.20
- 10:25