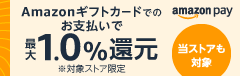職人の世界に飛び込んだ人たち
情熱を無駄にするのはもったいない 若き江戸切子職人・坂本優輝が見据える職人の未来
|
|

江戸切子の魅力は、その圧倒的な“美しさ”にある。あらゆる角度から差し込まれる光が反射し、繊細な模様を写し出だす。その儚い美しさに、不思議と惹き込まれてしまうのだ。 今回は、堀口切子に所属する江戸切子職人・坂本優輝さんにインタビュー。高校生で切子職人を目指した背景と、伝統を受け継ぐことに対しての想いを聞いた。
190年の歴史を持つ伝統工芸
 「籠目ニ菊繋文切立盃(かごめ に きくつなぎもん きったてはい)」 そもそも、“江戸切子”とはなんなのだろうか。坂本さんに、江戸切子という伝統工芸について教えてもらった。「江戸切子というのは、ガラスの表面を削ったり磨いたりと加工を施したガラス製品のことを言います。始まりは1834年、江戸の日本橋大伝馬町。加賀屋久兵衛(かがやきゅうべえ)という方が製作したのが始まりと言われています」 およそ190年の歴史がある伝統工芸、江戸切子。きっと当時、江戸切子を始めてみた人も筆者と同じくその美しさに目を奪われたことだろう。 そして坂本さんは、江戸切子に4つの定義があることを説明してくれた。「1つ目はガラスであること。2つ目は、手作業で加工をしていること。3つ目は、主に回転道具を使用していること。4つ目は、東京都近郊で作られていることです」 江戸切子と聞くとグラスに模様が彫られているイメージもあるが、いまの条件を聞く限りガラスであればほかにも作品の幅はありそうだ。「江戸切子はグラス以外にも、ぐい呑、照明の器具、トロフィーなどにも使われていて、柔軟で自由度の高い工芸なんです」 
とはいえ、どうやって手作業でここまで細かい模様を入れているのだろうか。坂本さんに、江戸切子の大まかな製作工程について教えてもらった。「まず最初に行うのが、“割り出し”という作業です。これは、カットの基準線を引く工程になります」 
坂本さんが修行を始めて最初に覚えたのも、この“割り出し”だという。「江戸切子の作業にはやり直しが効くものと効かないものがあるんですけど、割り出しは基本的にやり直せる作業になります。と言ってもこの割り出しには、江戸切子のノウハウが詰まっている大事な工程なんです。最初の基準になるので、そこがブレてしまったら元も子もないんですよ」 割り出しは、最初に書く設計図のようなものだろう。「割り出しでは必要最低限の縦と横の線だけを引いていきます。よく細かいカットの斜めの線も引くのですか?と聞かれますが、割り出しの線が増えると、割り出しにかかる時間も多くなり、カットをする際に分かりづらくなってしまうので基本的には引きません」 

江戸切子の設計図を見せながら、坂本さんは割り出しからどのように工程を重ねていくのかについて解説してくれた。「割り出しが終わったら、次は“粗摺り”という工程になります。粗摺りでは、まずはざっくりと模様を削っていきます。そのあと“三番掛け”という工程で、粗摺りの部分より細かくなめらかにカットを施します」 
「粗摺りと三番掛けには、ダイヤモンドホイールという工具を使うんです」そう言いながら坂本さんが見せてくれたのは、棚一面に収納されたダイヤモンドホイールの数々だ。作品に合わせて、使用するダイヤモンドホイールの粗さや幅が違うようだ。削る技術はもちろんだが、これだけある道具の見極めも、作品の出来栄えにかなり影響してきそうだ。 
ダイヤモンドホイールは、人工のダイヤモンドが埋め込まれている工具で、よくみると表面がキラキラしている。この工具を駆使して細かい模様が削りだされているということはわかるが、それにしてもあそこまでの細かさを出せるのはやはり不思議だ。 「三番掛けは目の細かいダイヤモンドホイールを使うのですが、目が細かいということは研削力としては落ちるわけです。削る労力を減らすためにも、最初に粗摺りでざっくり削る必要があります。その一方で、細かい文様を入れる箇所は粗摺りを通す必要がないので三番掛けのみで行うこともあります。製作工程として、すべての工程を必ず通らなければいけないわけではなくて、必要に応じて工程や道具を選択していきます」 
“ガラスを削る”という行為はあと戻りができない。もしズレてしまったり、間違えて削ってしまったらどうするのだろうか。「自分も結構そそっかしいタイプなんで…(笑)。当て間違えないように気をつけてはいますが、たとえば黒いガラスを取り扱うときは光を通してくれずダイヤモンドホイールが当たるところが見えにくいので、最初当てたときに基準線から少しズレてしまうということはありますね。でも、最終的に削る幅というのがあるので、削りながらその範囲内に収まるように調整していきます」 
そう解説し、坂本さんは目の前で削る様子を見せてくれた。筆者の体感だが、数秒のあいだにカットされている部分が増えており、「いま削ってましたか?」と心のなかで確認してしまうほどあっという間に、坂本さんは綺麗な模様を削っていた。坂本さんは27歳という若さながらも、職人歴は9年目になる。何気なく見せたプロの腕に思わず圧倒されてしまった。 そんな坂本さんが、覚えるのに1番苦労した工程は“磨き”だという。「磨きは三番掛けや石掛けのあとに行う工程です。樹脂製のパッドに研磨剤をつけて、削ったところをなぞるように磨いていきます」 
「綺麗に磨くには、親方や先輩の削った通りに手を動かさないといけないのですが、上手く磨けないと“磨き残し”といって、白っぽく残ってしまう部分が出てくるんです。当時はその磨き残しが出ないように磨こうと思ってもなかなか上手くできませんでした。その品物については納品日があったため、できるだけ早く仕上げようと思ってもなかなか仕上がらず、先輩の手を煩わせてしまったこともしばしばありました。今ではだいぶ習得しつつあるとは思いますが、まだ高みには至っていないなと思います(笑)」 9年目にしても「至っていない」と語る坂本さん。改めて、職人の技術にゴールはないことを感じた。以前の取材でも感じたが、どんな職人さんもずっと理想のクオリティを追い求め続けている。ものづくりに正解はない。だからこそ、理想を追い求める情熱がどれだけあるのかが試されるのだと感じた。
「情熱を無駄にしちゃうのはもったいない」

坂本さんが切子の世界を知ったのは、高校生のころだったという。「昔から流木を拾って木刀を作ったり、石を削って勾玉を作ったり、ものづくりが好きだったんです。あとは、色のついたビー玉とか宝石とか、キラキラしているものも好きでした。高校2年生の夏休みのときに、テレビで江戸切子の特集をたまたま見て。『すごく綺麗だな』って思ったんです」 「それからインターネットで江戸切子のことを調べていたら、『堀口切子』のことを見つけたんです。親方の作品や、『黒被万華様切立盃(くろぎせ まんげよう きったてはい)』を見て、“こんな素敵なものを作る職人になりたい”と思いました」  「黒被万華様切立盃(くろぎせ まんげよう きったてはい)」 坂本さんは当時、進学と就職でちょうど迷っていた時期でもあったという。そんな偶然のタイミングで切子と出会ったことも、大きかったのかもしれない。「先生に相談したら、『インターンをやってみたらいいんじゃないか』と言われたんです。でもインターンを募集している工房なんてそうそうないし、そもそも自分自身『インターンって何?』っていう感じでした。そしたら先生が話をつけてくれて、1週間インターンに行けることになったんです」 だが、告げられた行き先は『株式会社堀口硝子』だったという。「『株式会社堀口硝子』は、親方のお父さまの会社なんです。だから、あれ?と思ったんですけど、行ってみたらすごく歓迎してくれて江戸切子の作り方や歴史など色んな事を勉強させてもらいました。そのインターンの最終日にたまたま親方が堀口硝子の工場にいらっしゃって。堀口切子の工場を見せてくれることになったんです」 念願の『堀口切子』。坂本さんは、代表である三代秀石・堀口徹氏に、切子への思いを伝えたようだ。「あの1日がなかったら、ここに就職できていなかったと思っています(笑)。自分は本当に運が良かったんです」 
「いまは親方含め6人が働いているのですが、そのときは親方と先輩の2人でやっていて、ちょうどもうひとり欲しいなっていうタイミングだったようです。いまでも思うんですけど、この業界は入りたいと思って入れる業界じゃないというか。応募する人にとっても一期一会の出会いかもしれないですけど、その前に会社側が受け入れられる状況じゃなかったり、雇用するにしても体制が整っているかいないかなどもあると思います。つくづく、自分は運が良かったです(笑)」 そう笑顔で話す坂本さん。たしかに人生の出会いやきっかけは巡り合わせというものがあると筆者も思うが、本当にそれだけだろうかと、坂本さんの話を聞きながら思っていた。進路に迷っているタイミングで江戸切子を知ったことや、親方さんとの出会いはたしかに偶然かもしれないが、最初に「これを作る職人になりたい」という坂本さんの思いと行動がなければすべてはなかったことなのではないだろうか。 坂本さんは北海道出身だ。高校2年生の17歳、インターンとはいえ東京の職人の仕事場にやってくる行動力と勇気が、果たして自分が17歳のころにあっただろうか。 
当時の決断について振り返りながら、改めて職人に必要だと思うことについて坂本さんに聞いてみた。「『思い立ったが吉日』という言葉がすごくいいなと思っていて。何をするにも、やりたいなって思ったときが1番情熱に溢れているじゃないですか。それを先延ばしにしてしまったら、ちょっと自分のなかでサボる気持ちが出てきてしまうような気がして」 「やりたいって思ったんだったら、やってみればいいんじゃないって思います。これは職人の道を目指すことに限った話ではないかもしれないんですけど、そのときの熱量ってやっぱり自分がやりたいからだし、その情熱を無駄にしちゃうのはもったいない。自分みたいに運よく受け入れてくれるところがあるかは別なんですけど、人生1度きりのなかで、『やりたいな』って思ったことを、思ったときに行動に移すっていうのがすごく大事なんじゃないかなと今になって思います。もしそれが失敗に終わっちゃったとしても、その気になったら意外とどうとでもなるんじゃないかと思うので(笑)。いまを大事に生きることが大切なのかなと思います」
自分たちの生きる時間は、これからの伝統になる

職人として初めて手がけた商品は、『よろけ縞』だと坂本さんは振り返った。「縦線を連続で入れていくデザインなんですけど、このよろけ具合だったり、どれぐらい節をつけるかとか。シンプルに見えてすごく難しいんです。当時は、使っていないグラスを数十個ほど練習で使わせてもらってから、本番に臨みました。すごく緊張したのをいまでも覚えています」 「いまは当たり前のように、削って磨いて出荷をしていますけど、自分が手がけた商品が日本や世界の各地に届いて、誰かのもとで使われている。改めて考えるとそれってすごく嬉しく思う一方、『江戸切子』を作る一員としての責任感もあって、とても不思議な感覚です」 
堀口切子では、江戸切子を使ったジュエリーの制作も行っているという。伝統工芸でありながらも、新しいスタイルなどに挑戦し、日々作品も進化しているようだ。 「江戸切子の190年という歴史のなかで、変わっていない部分というのが伝統の本質だと思うんです。ガラスを削って磨くことだったり、誰かの手に渡ったとき、見てもらったときに『うわ、これすごいね』『綺麗だね』って驚かせたり、感動させることだったり。それが江戸切子の本質なんだと思います。堀口切子はその本質をすごく大切にしていますし、しっかりと踏襲していると思います」 坂本さんは、江戸切子という技術に対して語りながらも、こう続けた。「いまこの瞬間、自分が江戸切子職人として活動できる期間のなかで、精一杯できることだったり、務めなければいけない役目を大事にしながら、新しい自分なりの作品を作っていきたいと思っています」 坂本さんは、2023年の『第35回江戸切子新作展』で東京都産業労働局長賞を受賞(「RINKA」)。2024年の『第36回江戸切子新作展』で江東区議会議長賞を受賞している。2024年の作品「心祈万海(しんきばんかい)」は、刀を模した作品を制作した。 「この作品は自分のなかでも、けっこう象徴的な出来事だったかなと思っていて。江戸切子新作展で出品されている作品は大皿や鉢、花瓶などの形状のものが多いのですが、なんか…目新しくてかっこいいものを作りたいなって思って」 筆者も「心祈万海(しんきばんかい)」を最初に見たときは、「これも江戸切子なのか」と驚いた。これこそ、先ほど坂本さんが語っていた、“本質を踏襲しつつ新しいものを生み出す”ということなのではないだろうか。 「これからはいままでやってきていることを大事にしながらも、誰も見たことのないような作品だったり、人を驚かせて『すごい!』と感動してもらえるようなものを作っていきたいです」  「心祈万海(しんきばんかい)」 伝統的なものは、どうしても“変えてはいけない”という思いにとらわれがちだ。もちろん、変わらないからこそかっこよく、そこに愛が込められているという部分もある。だが、存在を残していくためには、次の世代が柔軟に新しいかたちへと変えながらも受け継いでいくこともまた、大切なことなのではないだろうか。 坂本さんの「本質を踏襲しながら新しいものを作る」という思いは、江戸切子に限らずすべての歴史、伝統、文化において言えることなのかもしれない。そのためには、まず本質とはなんなのかを見極めることが必要となる。 自分がいま触れている文化、日々行っている仕事、人とのつながりの“本質”はなんなのか。そのうえで、自分はどう行動していくべきなのか。今回は、江戸切子職人・坂本さんから大事な考え方を教わったような気がした。 |
|
- 2025.05.20
- 10:18
- 職人の世界に飛び込んだ人たち