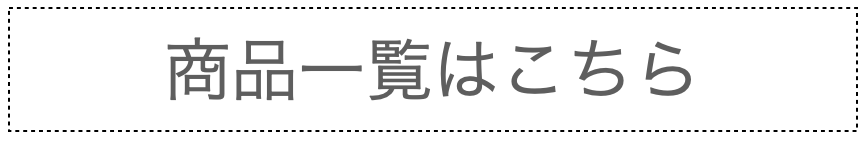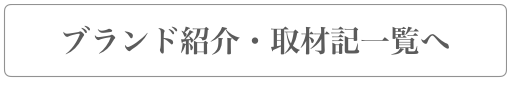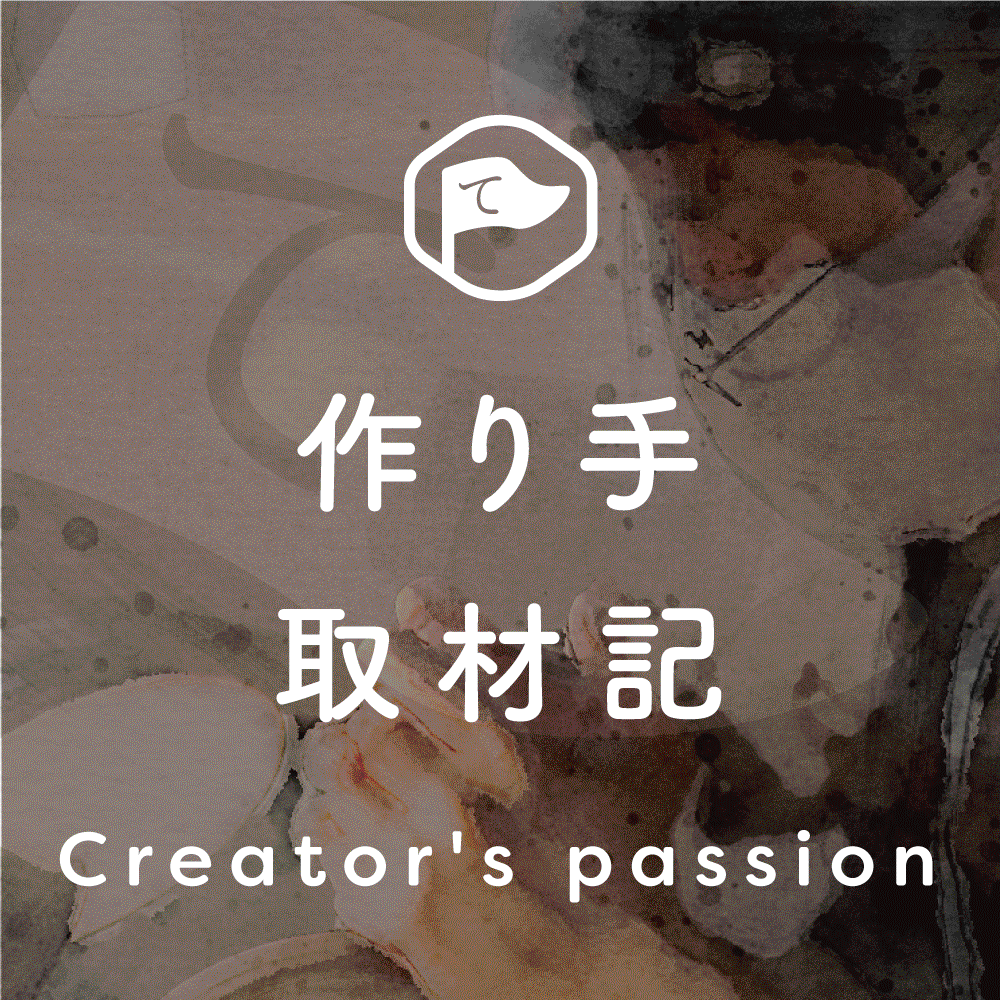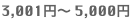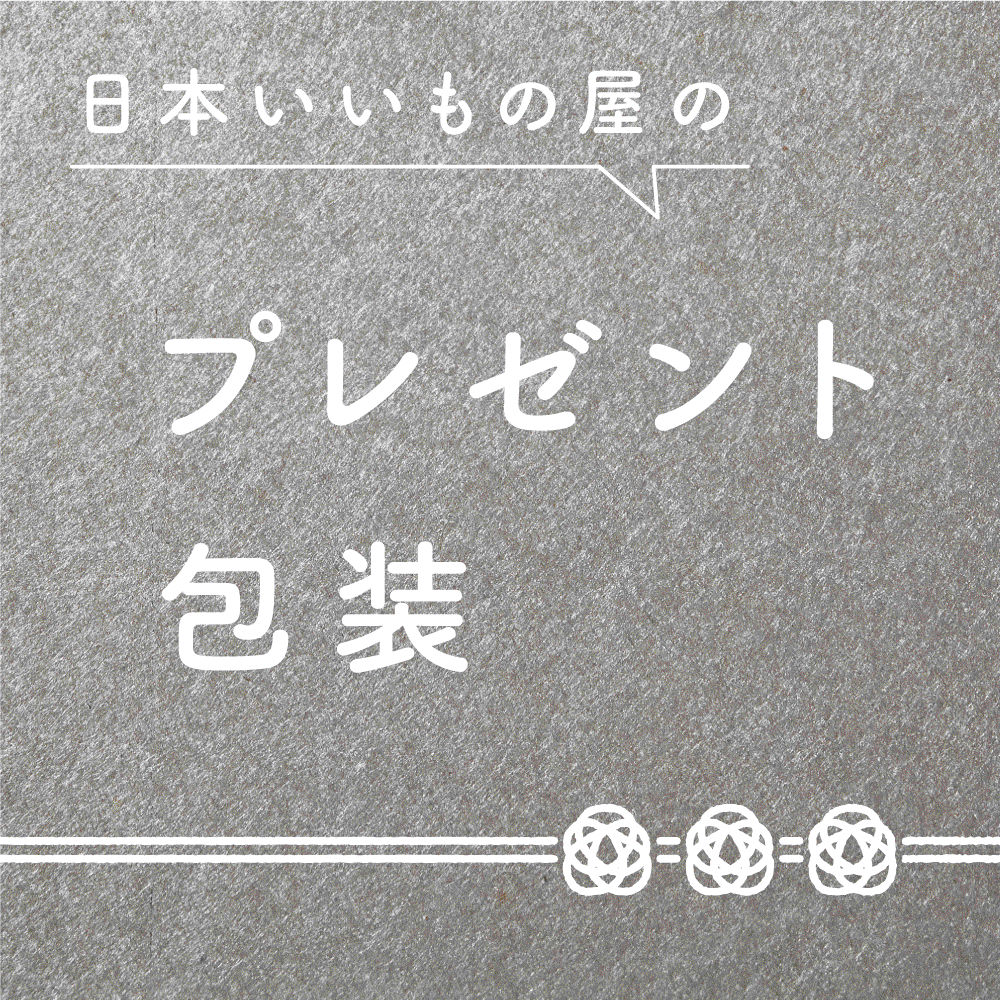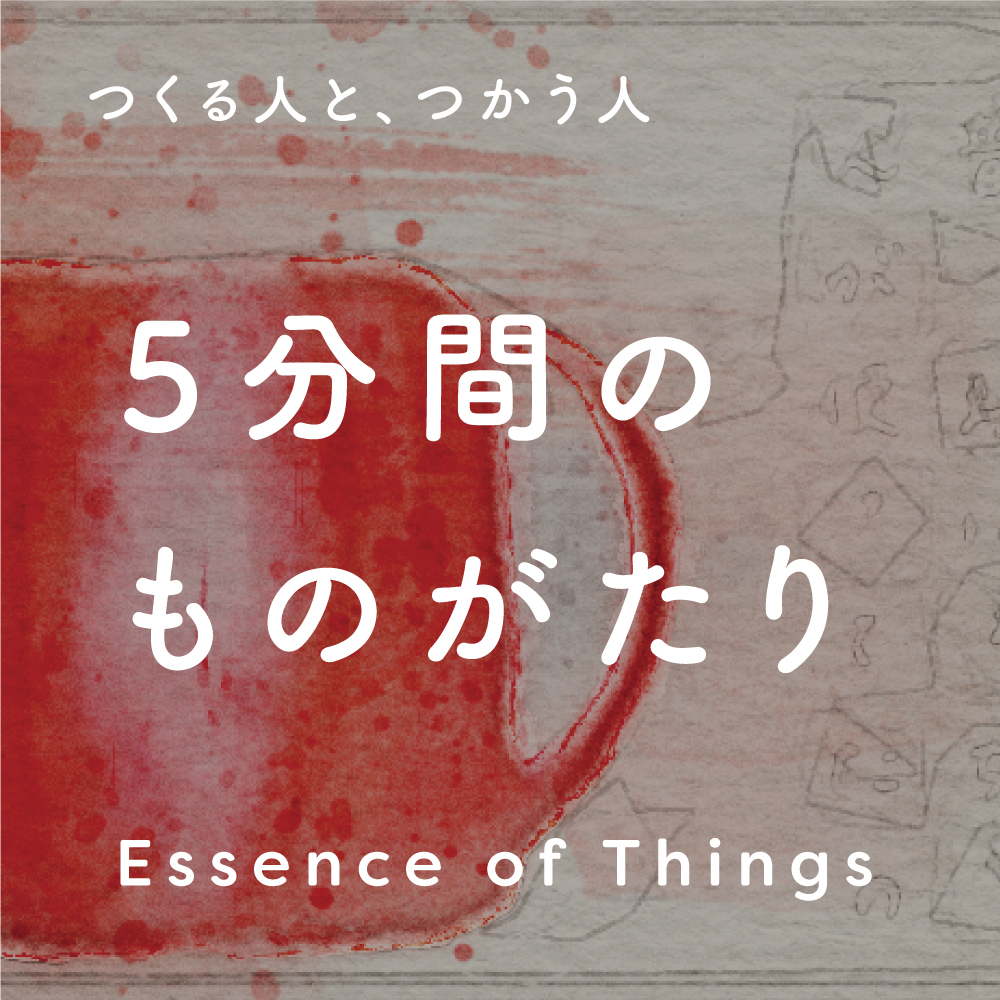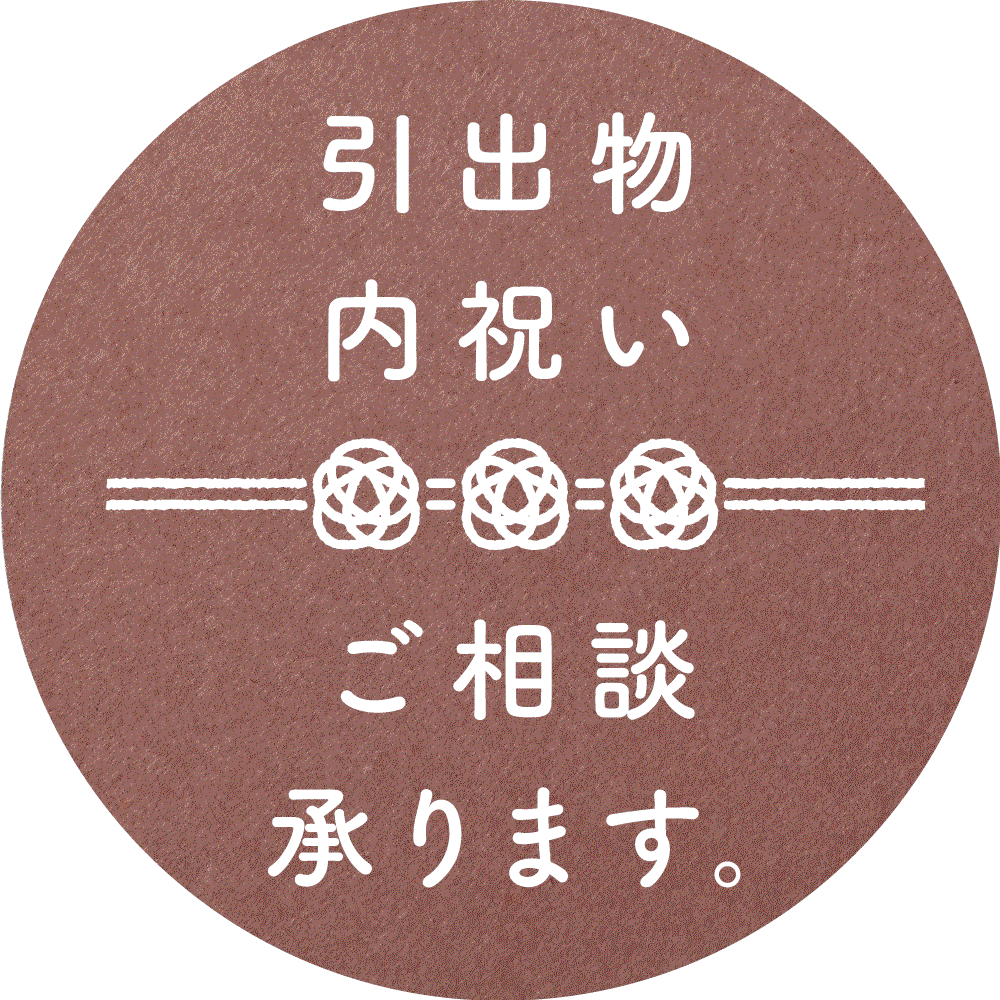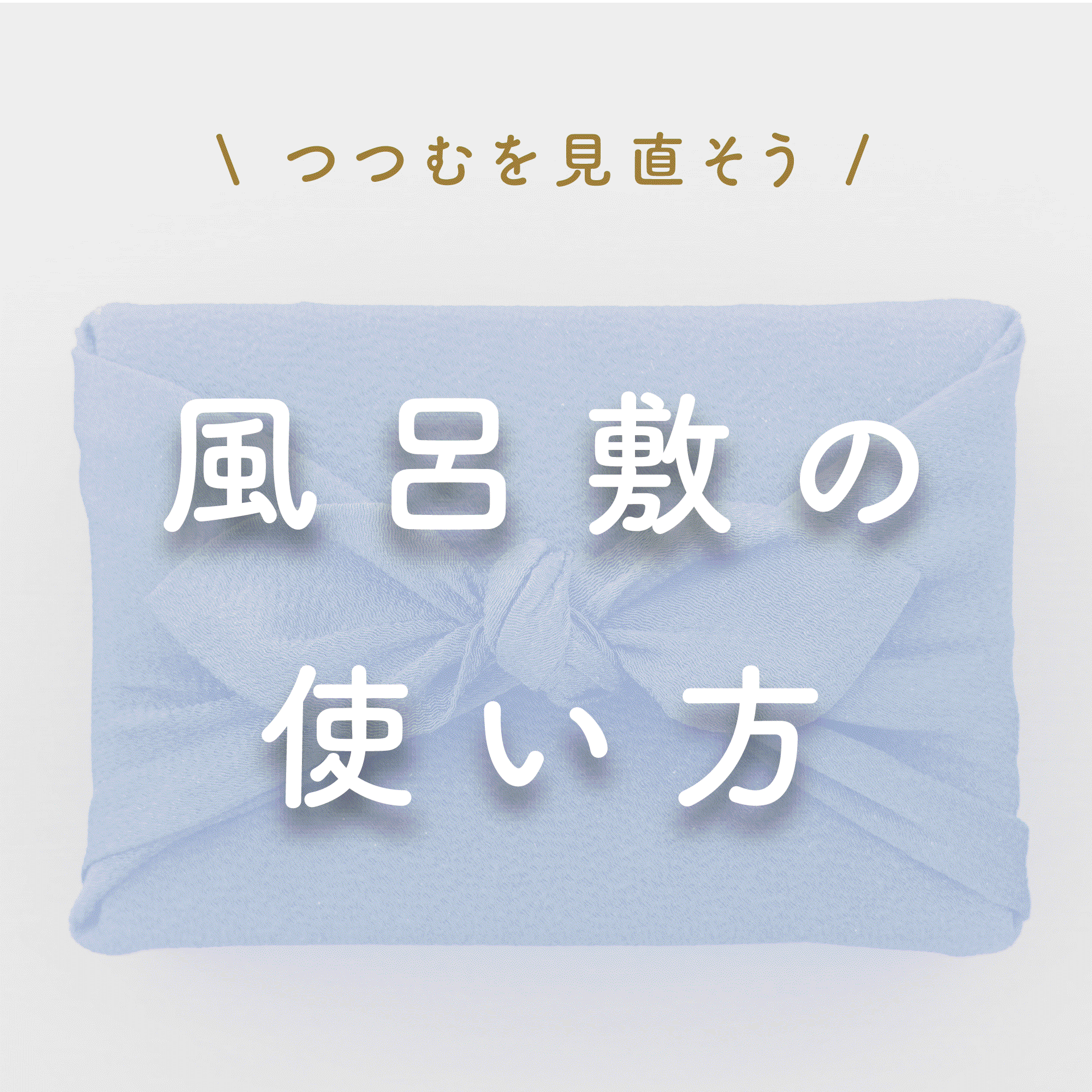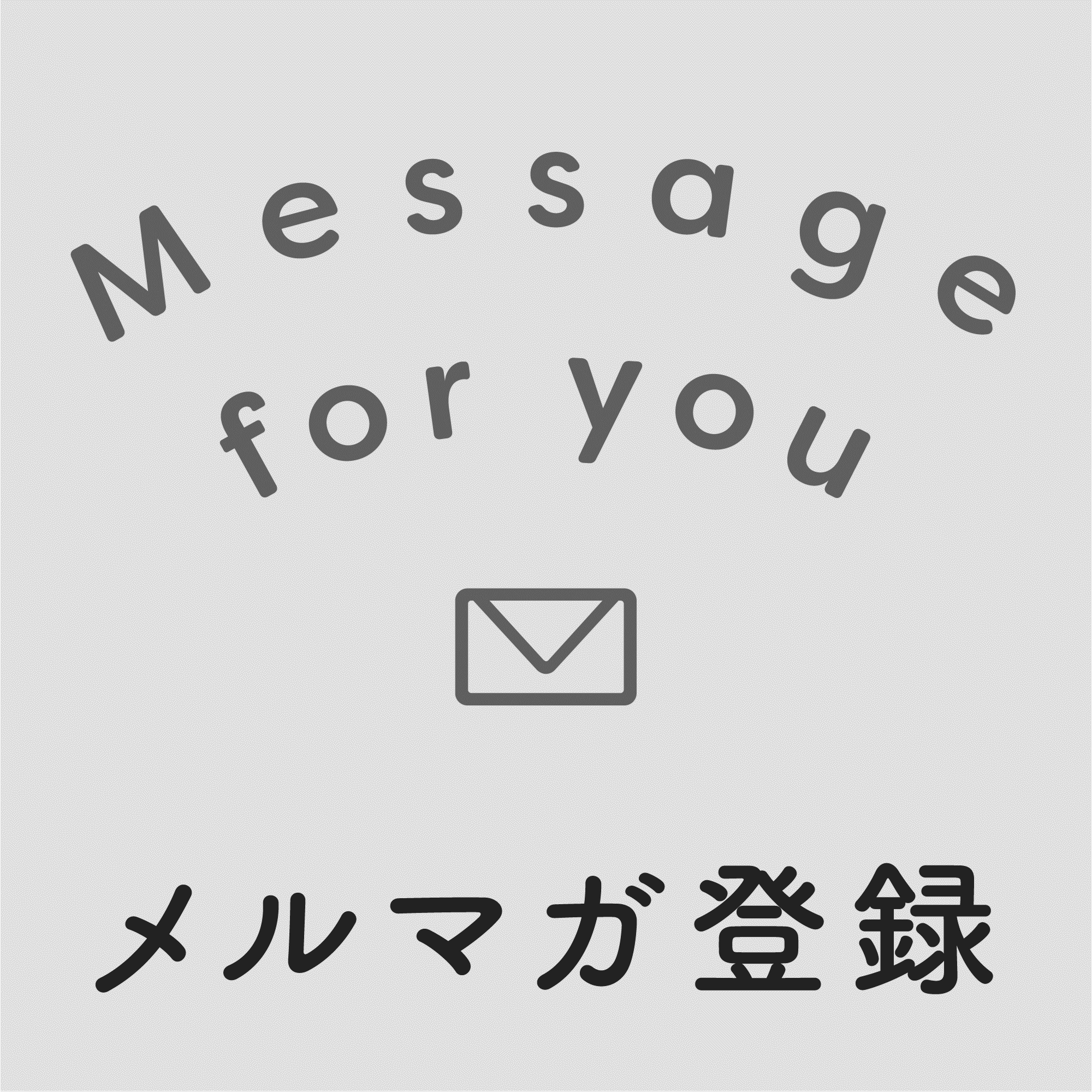ブランド紹介
kenema


kenema取材記
|
|
みなさん、手ぬぐいって使っていますか? タオルやハンカチの代わりに持ち歩いたり、布巾のようにキッチンで使ったり。色もデザインも豊富で、ファッショングッズやインテリアとしても活用できる万能アイテムです。 今回は、そんな手ぬぐいにフォーカスして取材記をお届けします。 ご協力いただいたのは、手ぬぐいブランド「kenema(けねま)」を手掛ける「宮本株式会社」の代表取締役・宮本善隆さんです。 昔ながらの、分業で作られる手ぬぐい あまり知られていませんが、手ぬぐいというのは分業制で製造されています。ひとつの注文が入ると、工程ごとに織屋、晒(さらし)屋、染屋といった各工場を回って、ひとつのものができあがる流れです。 そこで今回の取材では、宮本さんの会社だけでなく、kenemaの染色を担当する「株式会社ナカニ」の工場にもお邪魔して、貴重な染色現場を撮影させていただきました。 まずは、そちらの様子からお届けしましょう。 案内してくださったのは、代表取締役社長の中尾弘基さん(右)です。 実は、宮本さんと中尾さんは親戚同士。お二人の初代にあたるおじい様たちが兄弟で、当時は「お兄ちゃんが売るから弟が作る」という流れだったそう。 「大阪の堺市は、もともと綿花の栽培が盛んでした。その流れでこのあたりには江戸時代から晒屋があって、戦後になって染屋ができました。私たちの会社も戦後にできて、創業58年を迎えます」と宮本さん。 手ぬぐいの生地にも、種類がいろいろ まずは、現場を見学する前に、染める前の手ぬぐいの生地を見せていただきました。 手ぬぐいは、『小巾(こはば)』と呼ばれる幅の狭い生地を使用します。生地といっても、糸の太さや打ち込み本数、目の詰まり方などによって、さまざまな種類があります。 ここでは、違いが分かりやすい、文(ぶん)と特岡(とくおか)の生地を見比べてみましょう。 文は、少し厚みがあって目が粗く、生地にほのかな透け感があります。手ぬぐいのなかでも、伝統的な小紋柄などは、こちらの文生地を使うことが多いとか。 特岡は、目が詰まっていて透けにくいため、手ぬぐいの他、浴衣にも使われる生地です。目が詰まっている分、グラデーションなどの繊細な絵柄が綺麗に表現できるそう。  「kenema」では、一部の商品をのぞいて、特岡の生地を使用しています。 「特岡は、使えば使うほど柔らかくなるイメージがあります。糸って使い続けるうちに起毛するんですけど、そうなるとやっぱり糸の本数が多い特岡生地のほうが、個人的には触り心地良く感じますね」と中尾さん。 職人技が光る、注染の現場に潜入 kenemaの手ぬぐいは、伝統的な注染(ちゅうせん)という技法で染められています。 普通のプリントと違って時間も手間もかかる大変な技法ですが、染料の風合いやにじみが美しく、注染でしか出せない独特の“趣き”が魅力です。 ではさっそく、注染の工程を順番にみていきましょう。 まずは、先ほど見た小巾の生地を、丸いロール状に巻き直していきます。 なぜわざわざ巻き直すのかというと、このあとの「糊置き」という工程で生地を蛇腹に畳む必要があり、その際に生地を丸く巻いていた方が作業しやすいからです。 生地によりますが、だいたい1ロールで24mになります。これを1日で2000~3000mほど巻いていくそう。ものすごい量ですが、注染をはじめる前にこの下準備をしないと効率が下がってしまうので、とても大事な作業です。 ここからが注染の一番最初の工程にあたる、「糊置き」です。 生地の上に手ぬぐいの柄をかたどった型をのせ、海藻成分でできた糊を塗っていきます。この糊が防染の役割をするため、糊を塗ったところは染まりません。 糊を塗った後に型を持ち上げると、こんな感じ。このあとの「染め」の工程で、糊が塗られて白っぽくなったところは染まらず、糊が塗られていないところに色が入ります。 この泥のように見えるものが、糊です。「海藻成分を混ぜた糊なんですよ」とのことだったので、近づいて匂ってみると、確かにほんのりと潮っぽい海の香りがしました! 型の上から1枚ずつ糊をのせ、生地を折り畳んでは、また糊をのせ…と繰り返していきます。最初に見た「生地の丸巻き」がここで役に立っていますね。 職人さんはササッとスムーズに行っていますが、柄の位置がずれないように生地を置いて糊を塗るというのは、想像以上に難しい作業。生地をシワなく伸ばして置くだけでも、素人にはなかなかできそうにありません。 「手のスピード=生産量なんで、慎重にゆっくりやったら良い…というものでもないんですよ」と中尾さん。繊細さとスピード、両方が要求されるんですね。 手ぬぐいの柄に応じて、糊をつける分量も変わってくるそうです。すべては職人の感覚と経験が頼りなので、いろんな柄ができるようになるまで、最低5年~10年はかかるのだとか。 続いて、「染め」の工程に入ります。 糊置き後の折りたたまれた生地を染台にのせ、まずは「土手」と呼ばれる、囲いを書いていきます。染める色を分けるための作業ですが、まるでケーキに生クリームを絞っているみたいで面白いですね! 土手ごとに、それぞれ染料を注いでいきます。 注ぎ終わったあとに足元のレバーを踏むと、下から染料がシューッと吸い取られ、糊がついてないところに色が入っていく仕組みです。 50枚を一気に染めることができる、この注染の技法は大阪で生まれました。 「重ねて染めるっていうのは、量産することを前提にした手法です。“がめつい”って言うと、ちょっと聞こえが悪いですけど、大阪人の染めっていう感じで面白いですね(笑)」 表から染めたあと、ひっくり返して、裏からもう一回染めます。両面からしっかり染めるため、完成した手ぬぐいは、表も裏もキレイに色が入ります。どこから見ても美しいのが、注染ならではの特徴です(プリントの場合は表にしか色をのせないため、裏が白っぽくなります)。 染め終えた後は、染料が落ちにくくなるよう色止めの液体をかけます。 次は、「洗い」の工程です。 余分な糊や染料などをここで落とします。昔は川の水でやっていましたが、今は工業用水を使って機械で行っています。 こちらは脱水の作業。基本は家庭の洗濯機と同じですが、とても大きな脱水機で回していきます。 最後が、「干し」の工程です。 まだ裁断されていない、長~い状態の生地を高い天井から吊り下げるようにしてかけ、温風を使って乾燥させます。 普通の洗濯物でも乾燥機をかける場合は縮みが心配ですが、こちらも同じ。濡れた生地を高温でガーッと乾かすのはよくないので、床からの温風にはブルーシートをかけて、適度な状態になるよう調整しているそう。 「あとはこれを伸ばして、カットして手ぬぐいに仕上げていきます。そこは分業で違う会社さんがやるので、うちはここまでですね」と中尾さん。 大きな課題を抱える、業界の今 株式会社ナカニがある大阪府堺市は、手ぬぐいの他に包丁の産地としても有名ですが、そちらもほとんどが分業制で作られています。 「日本の物づくりって、分業の形態が多い。だから、どこかひとつの工場が欠けても製造できないんです」 ところが今、手ぬぐいの業界は厳しい状況に立たされています。 「このあたりの注染工場は昔、50軒以上あったと言われてるんですけど、今はもう3軒しかありません」と中尾さん。 「家族でやってる小規模なところを含めて、全国でも…20軒あるかないか。注染の職人自体は、もう100人とかそんなレベルじゃないですかね」 この状況は、注染工場だけではありません。 中でも一番存続が危ぶまれるのが、手ぬぐいの小巾生地を織る、織屋の職人さん。この周辺で今、後継者が決まっている織屋さんも、たった2軒しかないそうです。 「小巾の業界はなかなか新規参入が難しいうえに、次の跡継ぎが決まらず、どんどん廃業していってます」と中尾さん。 「今も織屋は70、80歳近くの人がやってるところが多くて。そういう現状を知ってもらって、『織屋でやっていきたい』と決意してくれる若い人が出てきてくれるといいんですけど」 後継者不足の問題は、日本の伝統的な物づくりの現場でよく耳にする課題です。 今まで受け継がれてきた伝統や文化が、途絶えてしまう大変な危機。しっかりとした対策をとらないといけないのですが、なかなか簡単にいかないのが現状のようです。 産地全体で、物づくりを続けていきたい 一方、株式会社ナカニの職人さんは若い方が多く、世代交代が上手くいっています。 「注染の手ぬぐいをどうやって作るのか、最近は表に出るようになっているので。それを見て、やりたいという若い人はいますね。ただ、やっぱり工場で残っていこうと思ったら、作業場の数を増やして、それなりに職人さんの数を抱えていかないと。ちょっと怪我したとか、病気で休んだりしたら生産が止まるようでは難しいですから」 中尾さんご自身は滋賀県出身で、婿養子として堺市にやってきました。外から来た目で見ると、最初は堺市の手ぬぐい業界にとても驚いたそうです。 「普通の住宅街の川沿いに、織屋も晒屋も染屋も…手ぬぐいの全部が集まっている。こんなにまとまった地域って、全国的にもここだけなんですよ」と中尾さん。 「だから『自分たちの工場だけが残ればいい』という考え方ではなく、産地全体で物づくりを続けていけるように、これからも手ぬぐいの魅力を発信していきたいですね」 注染手ぬぐいの「kenema」 続いては「宮本株式会社」に移動し、「kenema」について宮本さんにお伺いしました。「kenema」は2005年にデビューし、今年で19年になるオリジナルブランドです。 立ち上げた当初は注染の生地で子ども服を作っていましたが、現在は和のデザインを基調にした手ぬぐいをメインに手掛けています。 「kenemaを立ち上げる前も手ぬぐいはやっていたんですが、花柄や豆絞り、“祭”や“必勝“などの文字を書いた、いわゆる昔ながらのデザインしかありませんでした」と宮本さん。 それらも卸しでやっていたので、問屋さんを通じて流通していくことがほとんど。自分たちの社名が出ることもなく、どこで売られているのかも分からない状態だったそうです。 「当時は、今のようにデザイン性が高かったり、嗜好品として使われたりする手ぬぐいがほとんどなかったので。このkenemaで、それをスタートさせた感じです。今は、自分たちの商品を、自分たちの力で、自分たちの見える範囲で売ってもらっているので、そういった部分でも、やりがいとか喜びとかを感じられるようになりましたね」と宮本さん。 kenemaならではの魅力 自社ブランドとなると、これまでと動き方が全然違い、苦労も多かったと思います。 「最初は本当に手探りでしたね…」と当時を振り返る宮本さん。 それまでは問屋卸しみたいな形だったので、出荷はケース単位で出荷するのが当たり前でした。それが、自社ブランドになると、これだけの種類の商品を、これ1枚、これ1枚というようにピッキングして、伝票発行してそれを出荷するという流れに。 「本当にこれでいけるのかなっていう、不安はすごくありました(笑)」 それでも、これでやっていこうと気持ちを切り替えてずっと続けてきたことが、今につながっているそうです。 kenemaの魅力のひとつとして、日本の四季を感じる色や柄をベースにした「独創的なデザイン」があげられます。 春夏秋冬の風物詩や縁起物、日本の文化などをモチーフにしつつ、大胆さやユーモアを取り入れて作られた柄が豊富にそろいます。色数が多くて、鮮やかで、まるで一枚の絵のよう。そんなデザインはどうやって生まれるのでしょうか。 「当然、時代によってデザインもいろいろ変わってはいるんですけど。やっぱりうちのデザイナーが、より『こんなのができるんじゃないか』『こういうのはどうか』とバリエーションを増やしていった結果、今のこのデザイン性になってきてると思いますね」 今使いたい、手ぬぐい 手ぬぐいの動きとしては、kenema立ち上げ当初の十数年前と今とでは、何か変化があるのでしょうか。 流行りみたいな感じで、一気に世の中で手ぬぐいを見るようになった時期もありましたが、それも今はひと段落ついたのかなと思います。 「そうですね。今はどちらかというと、ひとつの定番品になっていると思います。流通という点で見ると、昔はなかったのですが、今はインバウンドの需要というがかなりありますね」 kenemaは、観光地のお土産屋さんに置かせてもらっている割合も多く、外国の方にも好評なのだとか。 日本を感じられる柄で、ストーリー性があったり、由来や意味合いがあったり、ユーモアがあったりする。そういったkenemaのコンセプトが、特に外国の方に受け入れられているようです。 ただ、今でも「手ぬぐいって何に使うの?」と聞かれることも多いそう。 私自身は、手ぬぐいをハンカチ代わりに使っています。パイル系のハンカチなどと違ってかさばらないですし、使っていると馴染んでくるので非常に使いやすいです。使い出すと抜けられない、心地よさがありますね(笑)。 「ありがとうございます。ほかにも、インテリアであったり、バッグに巻いてファッションの一部として使ったりもできますよ」 最近、私がいいなと思っているのが、手ぬぐいを飾って楽しむ方法。kenemaの手ぬぐいはとてもデザイン性が高いので、インテリアとして飾るのに最適です。 四季折々、季節に合わせたイベントごとの柄があるので、額やタペストリーにして気軽に飾れます。片付けるときは小さく畳めて、かさばらないのも魅力です。 「特に今はマンションに住んでいると、大きなひな人形やこいのぼりみたいなものは飾れなかったりするので。そういう節句やイベントの雰囲気を手軽に楽しんでいただけると思います」 業界全体の未来に向けて 最後に、会社の、ひいては業界全体のこれからのビジョンを教えてください。 「この業界そのものに、やっぱりいろんな課題とか、クリアしていかないといけない部分ってたくさんあると思うので。小巾綿布の素材であったり、注染とか、和晒とか、整理加工とか…いろんな分業制になっているすべての工程の技術や加工方法を生かして、新しい商品や用途開発というものをしていかないといけないですね」と宮本さん。 「ただ、長い目で見て会社を継続させていくためには、それプラス、違う柱を立てていかないと。これからもいろんな商材やデザインを検討しながら、お客様に感動と楽しさを伝えていきたいなと思っています」 跡継ぎ問題など業界全体として解決すべき課題はありますが、それでも現代まで続いてきた注染の手ぬぐいには、奥深い魅力と可能性があると思います。 この取材記を通して、その一端が少しでも伝われば嬉しいです。 長時間にわたる取材にご協力いただき、ありがとうございました。 |
|
kenemaの手ぬぐいバリエーション