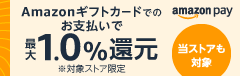ブランド紹介
工房アイザワ

|
|

|
|
工房アイザワ 日本の伝統工芸を生かす道具を作ることを掲げる新潟県の燕市の老舗道具店。モノがなぜ存在するか、なぜ必要か。常にそのものづくりの原点に忠実に向き合います。機能美を追求し、装飾性を削ぐことでモノに生命を吹き込む。 それが工房アイザワのモノ造りとその姿勢です。 |
|

工房アイザワ 取材記
|
|
金属加工の集積地で知られる新潟県の“燕三条”。特に燕市が作るスプーンやフォークなどのカトラリーは日本国内シェア95%を占めています。 今回は、そんなものづくりの町で大正11年に創業し、長く調理道具を作ってきた「工房アイザワ」にお邪魔しました。 取材に応じてくださったのは5代目の社長で代表取締役の相澤保生さんです。  工房アイザワさんは業態でいうと問屋さんにあたります。実際に製造されるのは同産地のメーカーさんたちです。最近ではメーカー発のブランドが多く見られるようになりましたが、その中でも工房アイザワさんが存在感を持っているのはなぜなのか? 日本いいもの屋としても基本的にはお取り扱いさせていただくブランドはメーカー発のものが多いのですが、なぜ工房アイザワさんをご紹介したいと思うようになったのか?今回の取材ではそれらの理由もわかっていただけると思います。 機能に向き合うことが出発点 工房アイザワの商品は、時代を超えて普遍的に使える道具が並びます。その背景には、常にそのモノが「なぜ存在するのか」という問いがあるようです。 相澤さんは、商品を作る上で「まず一番最初にはっきりさせないといけないのがその“機能”」と断言します。 「商品である前に“道具”。機能を曲げてしまったら道具にならない。かっこよさやデザインを先に追求すると、その道具がなぜ存在するかというメインのところがぼやけてくる」  そのため開発の際はデザインやシルエットから入らず、外部のデザイナーさんも基本的には頼まないのだとか。 商品の企画は全て相澤さんが担当し、「なぜその商品を作るのか」と機能から考えます。出発点はあくまで「機能」。  用途に合った材料は何か、どうやったら使いやすいか、あるいは持ちやすいか…。そのようなことを追求した結果、工房アイザワの特徴である機能的で丈夫な商品が誕生しています。 「その分シルエットはかっこよくないと自分では思っているんですけどね」と笑う相澤さん。  商品に惹かれるのは、きっと必要な機能が備わった“機能美”があるからなのでしょう。なにをもって“かっこいい”のか?なんとも基準が難しい問題ですが、私は工房アイザワの商品はかっこいいと感じています。 “機能美”がある商品は自然とかっこよくなる、のかもしれませんね。 時代を越える道具たち 工房アイザワは相澤さんの祖父によって大正11年に創業。地方問屋として始まりました。隣町の三条市で作られた農作業の道具をはじめ、人々が必要とするものを売っていました。 ものづくりを始めたのは3代目の相澤さんの叔父の代から。玄能(金槌の両方平たいもの)やカンナ、キリといった大工道具を作っていましたが、お客さんに「鍋を作ってくれ」と言われたのをきっかけに調理道具も作るようになったそうです。大工道具については電動化が進む時代の中で次第に作るのをやめ、調理道具にフォーカスするようになりました。 元々、会社がある燕市はキッチン用品の生産が盛んな街だったこともあり、調理道具を約50年作り続けて現在に至ります。  多くの店が時代とともに立ち行かなくなる中で、相澤さんは長続きする理由を「(商品を)道具だと思っている」からだと語ります。 「道具はいつの時代も道具。行平鍋だって江戸時代からあの形が続くのは、やっぱりあの形が正解なのかなって思う。デザインから入らない分、派手さはないし、カラフルさもない。よく言えばシンプルですけど悪く言えば単純。例えそれに飽きてかっこよさを求めても、結局元に戻ります。結局こいつらが正しいんでしょうね」。  この部分はとても工房アイザワさんらしい部分。追求した先にやはり同じ道具がある、こうしたものづくりのプロが試行錯誤しながら迷いながら行き着いたものを私たちが手にすることができる。なんだかそれだけでも贅沢な気がしてきます。 原点を見失わない。 コロナ禍、燕市では沢山のアウトドア商品が生産されました。コロナ禍でも楽しめるキャンプなどのアウトドアが流行し、燕市のメーカーさんや商社さんも売れるのであればと様々なアウトドア製品を作られたそうです。 確かに当時アウトドア商品が世の中に沢山出てきてキャンプなどのアウトドアブームがあったような印象です。現在でもキャンプなどアウトドアをする人は沢山いますが、一時期のブームのような時期は過ぎたように思います。 当時、相澤さんは周囲の会社がアウトドアブームに乗っていく中、アウトドア道具を作ることはされませんでした。  「たしかに魅力には感じました。でも、これやってその先どうするんだ?と考えるわけです」 「自分たちは何のためにやっているのか、会社をでかくしたいと思えばそれなりの方法があるけれど、規模は現状でもいいんだけれど納得したいものを作りたいという想いが強いんです」 相澤さん自身、流行りの波に乗ることは否定されているわけでは無いのですが、乗るのであれば乗り続ける必要がある。「でも少なくとも自分にはその才はないです」と、相澤さん。  自分自身をよく知り、会社の目的を見失わない。時代の流れや流行り廃りがあるなかでも、こうした原点を見失わない姿勢が、時代を超えて普遍的に使える道具を作り続ける工房アイザワさんを作り上げているのですね。 工程一つに妥協しない 商品のクオリティーの高さも工房アイザワの魅力です。100円ショップに調理道具が売られているように世の中には安価な製品が溢れていますが、「納得できる道具」を作ることに妥協しません。  例えばスプーン一つにしても、写真にある6工程以外に、倍以上もの工程があるとのこと。工程を省いたり、材料の質を落とすこともできますが、一つでも省いたらクオリティが大きく落ちてしまうそうです。 安く作ろうと思えば研磨だけでも4工程、5工程を省けるそうですが、考えの根底には「どうしたら道具として使いやすいか」という発想があるため「価格云々ではない」と。  実際にスプーンのようなカトラリーでは、バレル研磨(ドラム缶のような設備に石のようなビー玉のようなものの中にいれて回して研磨する工程)を1回で終えるのか、何度も行うのか。これによって仕上がりが全く変わってくる。 省けるけれど省かない、これがとても大事なポイントなのですね。 そんな相澤さんの1番の理想は「親から子へ、ずっと使い続けていくこと」だそう。カトラリー一つにしても引き継いでもらうことを考えるほどにこだわりをもっています。  価格でいえば安価なものはいくらでもある現代、なぜこの道具を使うのか・選ぶのか。すごく大事なことを教えられました。道具を選ぶ時「子供に使い繋げたいか?」と考える発想は大切なのかもしれません、使い繋げたい道具の後ろには必ず素晴らしいものづくり・作り手が存在します。 製造現場へ、職人の絶妙な手加減の積み重ね 燕市は分業が盛んな町。工房アイザワは自社に製造現場を持たず、理念を理解してくれる地場の協力工場や各地の職人と連携しながら商品を作っています。  金属やステンレスは、やはり金属加工が得意な燕市で。必要な金型などは工房アイザワさんがコストを負担します。 その他、竹の商品は竹細工で有名な大分県別府市で作ってもらったり、漆は漆が得意な石川県の片山津にお願いしたりと、日本各地のその素材が得意な地域と手を組んでいます。自社に現場がない分、いろんな種類の商品を作れることが強みになっています。 今回はその中でも燕市のステンレスの鍋やタンブラーなどを加工している工場を案内してもらいました。  作業は職人が機械に向き合い丁寧に手作業で進めていきます。一見簡単そうに見える作業も、実は職人の絶妙な手加減とちょっとした工夫の積み重ねがあり、他に誇ることのできるクオリティが保たれています。  例えば鍋の取手。  機械で曲げる前に一つづつ人の手で油を塗ります。そうすることで金属に傷をつけずに曲げることができています。  また、こちらは製品の蓋になるパーツ。  素人の目ではわからない金属の目の方向を瞬時に見分け、その方向に沿って丁寧に機械で磨きをかけてツヤを出していました。  これはあくまで1回目の研磨。すでに綺麗に見えますが、この後の工程で2回目の研磨をするそうです。その時の金属の生地によっては、さらに工数が増えることもあるそうです。  こちらはケトルの持ち手をつける工程です。製品に傷がつかないようにカバーをしながら丁寧に作業をされていました。  このように機械の作業に「人の手を入れたい」という思いは相澤さんの先代たちから引き継がれる思いです。そのような思いが工房アイザワの商品のちょっとした温かみや自然な形につながって、ここまで続いているのですね。 
取材を終えて 燕市をはじめとする各地の工場とコミュニケーションをとりながら、長く支持される商品を作り続けてる工房アイザワ。  シンプルに見えてもどこか他とは違う、一線を画した雰囲気がありますが、原点からぶれず、使いやすい道具を作るために細かい部分も妥協しない姿、作り手の小さい気遣いを積み重ねる姿をみて納得しました。  相澤さん、工房アイザワ、工場のみなさん、取材に協力してくださりありがとうございました! |
|

ミマツ工芸 / M.SCOOP

|
|


|
|
ミマツ工芸 / M.SCOOP 佐賀県南部にある筑紫平野にミマツ工芸の工房はあります。 家の中で、埋もれがちなアイテムに居場所をあげよう。という想いからM.SCOOPは生まれました。 「置く」という些細な動作を、愉快なワンシーンに変える。シンプルで上質なものを作り続けています。 |
|

ミマツ工芸 / M.SCOOP 取材記
|
|
古来から日本人の暮らしと共にあった木材。機能性だけでなく、木材ならではの温かさや安心感が私たちの生活を支えています。 佐賀県と福岡県の南部にまたがる筑紫平野の中心に位置する大川は、日本最大の家具生産地。今回は木工業が集まる大川の地で、暮らしに心地よさをもたらす木のプロダクトをつくる「ミマツ工芸」にお邪魔しました。 「ミマツ工芸」は現在、三つのブランドを持っています。大切なツールに置き場をつくる「M. SCOOP(エムスコープ)」、国産の杉の木目を生かした日本伝統の模様の贈り物「NENRIN(ネンリン)」、暮らしに花や自然の表情を取り入れる「GREEN(グリーン)」。 家具のまちで家具を大量生産していた時代から、「つくりたいものをつくる今」にどのように至ったのか。ミマツ工芸がたどってきた足あとを紹介します。  8月上旬の佐賀県神埼市。「ミマツ工芸」は青々とした田んぼに囲まれていました。 取材に応えてくれたのは、代表取締役社長の實松(さねまつ)英樹さんです。  ショールームに入ると、洗練された木製品が棚に陳列され、心地の良い木の香りがしていました。 大量生産の時代から自分が作りたいブランドへ 「ミマツ工芸」は實松さんの父親によって昭和47年(1972年)に創業しました。シンプルな家具が好まれる現在と違い、当時はヨーロッパ風の装飾が施された家具の需要が高い時代。大川家具を分業で作る地元で家具がどんどん売れる時代の流れに乗り、菓子職人をしていた父親は木製のテーブルの足を作るための会社を立ち上げました。 一帯では木工工業がどんどん栄えていきました。元はテーブルの丸い足だけを作っていた父親の会社も工場を拡大して大型の機械を導入し、婚礼タンスの引き出しを作ったり、取手や枠も作ったりするようになりました。  實松さんが若い頃は、朝の8時から夜中の12時まで働くような時代。そこまでしないと生産が追いつかないほどの勢いでした。ただただ発注された部品をがむしゃらに作る日々。お客さんの顔が見えない商売に「こんなに大量なものがどこにいくんだろう」「本当にどこかの家に入っているのか」「いつかは仕事がなくなるんじゃないか」という疑問や不安があったそうです。 30代になり、實松さんは会社の将来を考えるために先進地の視察などいろんな場所に出かけ、いろんなものを見て回りました。「うちの会社だったらどんな魅力あるモノがつくれるのか」。考えながら、2006年40歳を機に自社製品開発事業をスタート。2008年に自社ブランド「M. SCOOP」を立ち上げます。 初めはバイヤー主体で「こんなものなら買いますよ」との言葉を受け、iPodやiPhone関連の商品を開発し作っていた實松さん。「自分は、どうかなー?と思っても買い取ってくれるからしょうがない。そんなものづくりでいいのか」。そんな疑問が湧いて、「自分が欲しいと思うモノや、大切な人の贈り物にしたくなるモノを作る」ためにリブランディングも着手しました。これまでは作ることに徹していた實松さんですが、リブランディングを行うと決めてからは、自らお客さんとの窓口にもなりました。  当時はスティーブ・ジョブスが活躍していた時期。「あんなスマートなもの(iPhone)を持って軽やかに仕事をこなすような男になりたい」という憧れから「そんな男性になりたいなギフト」「かっこいい男性になってよギフト」をつくる方向性が固まりました。 国と時代を超えて愛されるものに心地いい置き場所を 「iPhone、腕時計、メガネ、ペン」。この四つは實松さんが毎日必ず会社に持っていくもの。さらに共通するのは、どれも實松さんが好きなものであるということ、いつの時代も変わらないであろうということ、万国共通であるということ。「変わらないものを絶対的に永久的に使っていきたい」という想いで、この四つに関連するものを作ることにしました。  デザインはプロにお願いし、實松さんはそれを形にする。当初開発会議の際、作りたいモノを説明しても「売れ筋じゃないよね」と言われることもありました。特に、腕時計置き。實松さんは以前から、机にわざわざ卓上時計を置くのではなく、自身の腕時計をデスクウォッチにしたいと思っていた気持ちとイメージを説明し「売れなくてもいい、同じように思っている人が多くなくても何人かいるはずだからそれでいい」と自身の想いに沿い、開発をスタートしました。  そうして生まれた腕時計スタンド「D. Watcher(デーウォッチャー)」、今ではブランドのベストセラーです。  「メガネ置きは、ミマツ工芸の原点であるテーブルの足をイメージしました」と、デザイナーの一言に、「すごい、さすがプロだ!」と感じたそうです。色は何年かに一度、「その時に感じた色」をリリースしています。写真に写っているのは「地域の色」。一つひとつ絶妙な塩梅で調合し、塗装は地元の信頼できる会社にお願いして表面の質感にまでこだわっています。 「僕らが良いと思うものを、多くなくても共有できる人に届けていければいい」という納得できるやり方で、「その時に出会った人や場面、感じたもの、大切なものから新しいものが生まれる」と實松さんは語ります。 ヨーロッパで与えられた課題から生まれた「NENRIN」 2015年と16年。世界に進出したいという思いもあり、以前から「世界で一番魅力的な展示会」と聞いていたパリで開催される「MAISON&OBJET(メゾン・エ・オブジェ)」に「M. SCOOP」を出展しました。 一つ一つ手を抜くことなく、どこから見てもきれいに仕上げた自社の製品たち。来場者がペン立て一つにしても隅々まで注目してくれたのが自信につながったと言います。「自分で会場を見て回っても『僕らが作っているもののクオリティーは高いんだ、いいものができているんだ』と感じることができました」と實松さん。一方で、日本で販売している価格と海外の人が出そうとしてくれる何倍もの価格のギャップに課題を感じたそうです。  もう一つ課題になったのは「なぜアメリカの木を使っているのか」という来場者からの問い。地元の家具業界では九州にない広葉樹をアメリカから輸入するのが当たり前でした。「日本には木が生えてないの?」とまで言われてしまい、「自分の地域に何があるか」「日本らしいものはなんなのか」という模索が始まります。  模索を始めて思い出したのは、1998年から實松さんがコツコツと作り直売していた年輪時計。佐賀県産の杉の木目を生かした丸太時計で、退職や還暦、米寿などの節目に、その人の歩みをたたえて贈るメッセージ性のある商品です。切り倒してから加工するまでには一年ほど上手く乾燥させなければならないため、作れる数はかなり限られていましたが、お客さんの顔が見えない商売をしていた時代でも、唯一お客さんと直接やりとりをして「買っていただいた喜び」と「自分の仕事が本当に喜んでもらえている喜び」を確認できる商品でした。 ただ、佐賀の杉の木は形も色もバラバラで「シンプルで美しいプロダクト製品が生み出せるような素材ではないと思っていた。」と實松さん。そんな時に「年輪経営」を掲げる大手自動車メーカーから自社の森の杉を使って毎年製品を40、50個つくってほしいという依頼を受けます。  「その時に向こうから送られてきた木が、ぎゅっと小ぶりできれいな丸太でした」。初めてここまできれいな杉を見たという實松さんは「こんなきれいな杉だったら何かプロダクトができるんじゃないか」と、新たな「年輪時計」プロダクトに取り組む事にしました。 こうして試行錯誤しながらたどり着いたのが、国産の杉の木目を生かして日本伝統の吉祥文様に仕上げた新しい年輪時計です。  「一本の木からつくる」ことに意味がある従来の年輪時計の思いはそのまま、さらに「おめでたい」ことを意味する日本伝統の紋様を自然の木目で表現することで、杉の美しさと日本らしさがつまった商品のブランド「NENRIN」が完成しました。現在、年輪時計は商標登録されています。 
足元にある楽しさを 一方で「GREEN」は、一輪挿しを生活に取り入れるためのブランドです。テーマは「日常の足元」。野草が好きな實松さんが、野草があることで感じる「いつも行き来する道でのワクワク」を共有したいとの想いから生まれました。  「野草は、風に揺れる細く繊細な茎や葉っぱが絶妙に美しく、つい眺めてしまう。しかしこれは流石に作れない!だったら、それに合うものを開発し心地良い暮らしの場をつくろう」という想いで商品ができています。 使われる木材は、自然にしかない個性や表情、美しさを代表するものたち。そこに、一輪挿し用の試験管などが付いています。 展示会がある時には、東京でもどこでも街中を散歩して自分でとった野草を持参しています。「ビジネススーツを着て、野草を持って歩いてるような男性、そういうスタイルいいと思いません?」と實松さんは笑います。 
杉の美しさを最大限に引き出す選別 ここからは、工場内を見学させてもらいましょう。  ミマツ工芸では、實松さんが試作品をつくった後、従業員に一つ一つ作り方を教えながら切る、貼る、組み立てるなどの作業を任せます。「同じものを作れないと製品化できない」。再現性が求められるため、試作品から製品化するまでに数年かかることもあるそうです。  木の選別は全て實松さんが担います。  こちらは年輪時計用に自社でブロックにした杉。ブロックにするのも精度を出すのが難しい作業です。實松さんは木ごとにまとめられたブロックを指差しながら「これはきれい、これはきれいじゃない、これは美しい絵にならない、この赤みはきれい」と一瞬で全体のイメージまで見極めていきます。素人の目には全てがきれいに見えましたが、こちらには分からない絶妙な色や木目の違いがあるようです。面によっても表情が違うため、一番美しい吉祥文様になるよう「市松」にするのか「波文」にするのかなどを決めていきます。  世の中には、ガラスや金属等、素材の良さを生かした魅力ある製品がたくさん存在しています。「僕は、木という素材が持つ個々の表情の違いを最大限引き出した美しいモノが、僕のつくりたいもの」と實松さんは語ります。 作家ではなくインダストリアルの仕上げ方  こちらは「M. SCOOP」のペン立てにもメガネ置きにもなる商品。お客様の要望から生まれました。ここから内側にフェルトを貼ったり、塗装をしたりして仕上げます。 木の削り方は素材に合わせて調整します。「試作品を一つ作る際は、極端な話一個一個調整すれば形になる。しかし、僕らが作るのは均一な精度を保った製品」と實松さん。「『削った状態が仕上がり』ぐらいのレベルにしなければ整わない」、「あとで補修するという気持ちは基本持たないようにしたい」と話します。 特にこの商品は、縁の数ミリの幅を均一にするのが、デザインのポイント(生命線)です。いくつもの工程を経て、ようやくこの形になるそう。磨きの工程でも、この絶妙な角を生かすのがポイントです。  こちらが完成品。このような細かい積み重ねが、一目できれいだと思える商品につながっているのですね。 
取材を終えて  ペン立て一つにしても「多分こんな(こだわって)やってるのは珍しいかもね」と嬉しそうに言う實松さん。自身が本気で楽しんで納得できる仕事をしているのが伝わってきました。 「自分がどうありたいか」「どうあったら自分がもっと心地いいのか」。 注文された数をがむしゃらにこなしていた下請け時代と打って変わり、實松さん自身が変わらないものに目を向けて、心地よいものづくりを追求するようになりました。そうした中で、その時々の出会いや感性が商品に生かされているからこそ、私たちの暮らしにも心地よさをもたらすものができているのだと感じます。 「生み出す製品は、永久デザインの想いを持って作っていきたい。常に改良を続け、もっともっと本物の機能を追求していきたい」と語る實松さん。これからも目が離せません。 實松さん、ミマツ工芸のみなさま、長時間にわたる取材にご協力いただき、ありがとうございました! |
|

M.SCOOP / ミマツ工芸 の商品一覧

スマホスタンド
Mobile catcher |

ペン立て兼ペーパーウェイト
p-pen place2 |
|

腕時計スタンド
D.Watcher |

メガネ置き
GLASSES PLACE |
|

ペン立て
70G case |
clife / 宇内金属工業

|
|

|
|
clife / クリフ 金属、革を使用した雑貨で心地良い日々を生み出すライフスタイルブランド。 私たちの仕事は『リラックスした日常』をテーマに、あなたの日々の暮らしをほんの少し心地良くする事。 メイドインジャパン・メイドインオオサカ。金属加工技術とレザークラフト技術、デザインの力で人々の気持ちに寄り添う製品を提案。 |
|

clife (クリフ) / 宇内金属工業 取材記
|
|
みなさんは、使えば使うほど魅力が増していく“経年変化”という言葉をご存じでしょうか。 本革や金属、木材、デニム生地などをイメージしていただくと分かりやすいと思いますが、長い時間をかけて使い込むことで、色や質感が変化することを指します。 使う人の個性によってその変化がひとつひとつ異なることから、「育てる」と表現されることもありますね。 当店でも経年変化が楽しめるアイテムをたくさん取り扱っていますが、なかでも今回は、革と金属を組み合わせてオリジナル商品を生み出す「宇内(うない)金属工業」にお邪魔しました。 訪れたのは、大阪市東成区。 製造業が多く、モノづくりが盛んな地域のひとつです。  お話をお伺いしたのは、装身具事業部企画課副部長の中村 拓也さん(右)と、企画・営業の石原 実千瑠さん(左)です。  宇内金属の自社ブランド「clife (クリフ)」では、さまざまな商品を展開しています。   すべて社内で一貫生産されており、機能的ながらユニークなデザイン性と、素材へのこだわりが魅力です。  今回の取材では、その誕生秘話から商品に込められた想い、製造現場の様子までたっぷりお届けします。 培われた、デザインの経験 clife (クリフ)の商品は、他の革小物ブランドとはひと味違う、個性的なデザインが目を引きます。 これらをすべてデザインし、形にしてきたのが中村さんです。 でも実は、最初から現在のような商品を専門に作ってきたわけではないそう。 「僕が20代で入社した時は、毎日ベルトのバックルのデザインばっかりやってました」と中村さん。  当時はまだ、物作りも販売もすべて国内で完結していた時代。 日本人が使う物は、日本人が作って、日本人が販売するのが当たり前でした。 「ところがいつの頃からか、海外に買い付けに行ったり、工場が移転するようになったりして、徐々に国内産業が衰退していったんです」 時代の流れにあわせて、中村さんの仕事も少しずつ変わっていきます。 今までは日本製のバックルだけだったのが、台湾製のバックルもデザインするようになり、また数年後にはバックルだけでなくベルト全体のデザインにも携わるように。  さらにはお財布もデザインするようになり、どんどん仕事の幅が広がっていきました。 モノ作りへの、熱い想い 「特に財布のデザインって、構造上どうなっているか、わりと緻密に設計していかないと、つじつまが合わなくなってくるんですよ」と中村さん。 「この財布ってどういう構造をしているんだろう」というのを現物を見ながらじっくり調べ、紙を使って自分で財布を試作し、それをお客さんに見せながら製品にしていったそう。 「そうやって設計のノウハウみたいなものを自分の中で作っていけたのが、30代の頃でしたね」と中村さん。 ところが、その状況もまた少しずつ変わっていきます。  「直接中国に工場を持つような会社さんが出てきたり、金具をもっと安く海外で作って販売する業者さんもどんどん増えはじめて。流通経路の中で、少しずつうちの仕事が減ってきたんです」 中村さんが40代の頃には、デザインの仕事が急速になくなってしまったそう。 「その頃の僕は暇になってきたんで、会社のこととか仕事のこととか、 自分の関わってることに関して、色々深く考えていました」と中村さん。 会社の中で製品のデザインに携わってはいるけれど、実際に製品を作っているのはメーカーさんで自分じゃない。 もともとモノ作りに興味があった中村さんは、もっとモノ作りに関わりたいという気持ちが高まり、仕事とは別の趣味として、カバンの製作教室に通い始めます。 ここが、中村さんのすごいところです。 普通は自分の仕事が減ってしまうと意欲も落ちてしまうものですが、中村さんの探究心は尽きません。 やっぱり“モノ作りが好き”という想いが、根底にあるからでしょうね。 「どんな形のパーツが組み合わさって、この形になっているか。バラバラに開くとどういう形をしてるか。そういうのを考えるのがわりと好きで。頭ん中でずっとシミュレーションしたりしています」 転機となった、カバン製作 「カバン教室に通っているときが、『人生の中でいちばん楽しい!』っていうくらい楽しかったです」と笑顔で語る中村さん。 できることが増えてスキルがあがってくると、今まで趣味でしていたカバン作りを会社の仕事に生かせないかと考えるようになります。 「僕の仕事も減ってきていたし、このままこの状態でいるのは良くないな、と。でも自分にできることっていったらカバン作りくらいだったんで、 じゃあ会社の中で1回カバンを作ってみようと思って、Caramel(キャラメル)というブランドを立ち上げたんです」  自社でブランドを立ち上げるのはまったくはじめてのことだけに、社内で反対する意見などはなかったのでしょうか。 「わりと自由にさせてもらえたんで、その点はとても恵まれていました。『あんまり無茶するな』とは言われましたけど(笑)」と中村さん。 宇内金属は、エアコンや自動車の部材といった工業製品を手掛ける事業部がメインで、中村さんが所属する事業部だけがファッションにまつわるものを手掛けるちょっと特殊な立ち位置だったことから、ブランドに関することは中村さんにすべて任されていたとか。 「金属 × 革」で、独自の色を Caramelは中村さんがカバンを作り、販路も色々探しながらやっていたのですが、1人で手掛けていたため「もっと伸ばしていこう」と思っても、量産できないのが難点でした。 「もうちょっと量産に向いてる製品を作りたいなと思いました。うちはもともと金属加工会社なんで、どうせならその金具と革を組み合わせたブランドを作ったらいいんじゃないか、と」  一般的に、金属加工の会社は金属加工ばかり行いますし、革製品を作る会社は革製品の製造ばかり行います。 「うちなら両方できるから、自分たちらしいものができるのかなと思って。金属と革を使って、自分たちでデザインからスタートして、制作まで全部やっちゃう。他のメーカーさんが真似したくてもできないブランドになると思ったんです」 こうして誕生したのが、clife (クリフ)です。 --- ブランドの惹かれたポイント --- 代表 裏家 私も実はこういう背景・ストーリーにとても惹かれました。 革製品を好きな方はとても多いので、日本いいもの屋でもご紹介できるような革製品ブランドはないかな?と探していました。 革製品という分野は作家さんも多くいる分野ですし、作ることそのものはそれほどハードルが高くありません。ですので、素敵なデザインの革製品は沢山見つかるのですが、「日本のものづくりを伝える」というお店のコンセプトにも合ったブランドがなかなか無かったのです。 でもclife (クリフ)は全然違った。金属加工をスタート地点にしています。金属部分が軸にあって革製品を生み出すブランドは知る限り他にはありませんでした! 成り立ちが特殊なので誕生する商品にも特徴があります。金属加工が一からできるので、金属パーツの素材や形状や加工方法でもこだわることができる。他に真似できないパーツがあるので、人とは違うものを探す人にはぴったり。 実は私たちの拠点も東成区。こんなに近くに探していたものがあったとは、、まさに灯台下暗しでした。 金属だけじゃない。革にも永く使える良いものを clife (クリフ)は、金属部分だけでなく革素材にも並々ならぬこだわりを持っています。 製品に使う革は、すべて「ピットなめし」という製法で作られたもの。 「なめし」とは、牛の原皮が腐ったり変質したりしないように加工する作業のこと。 なめすことで原皮が革へと変化し、私たちが使う革製品になっていくのです。 なめす作業には、植物の渋であるタンニンを使用します。 一般的には「ドラムなめし」といって、ドラム槽に薬剤と原皮を入れてぐるぐると回しながら短時間でなめす製法が主流です。 一方「ピットなめし」は、プールのような槽に原皮をつけて、ゆっくり時間をかけながら徐々になめしていく製法です。  中村さんはなぜ、ピットなめしにこだわるのでしょうか。 「ドラム式洗濯機をイメージすると分かりやすいのですが、ぐるぐる回すと服の繊維がほぐれるじゃないですか。原皮も繊維が密に絡み合ってるものなんで、やっぱりほぐれちゃうんですよ。でも、ピットなめしだとゆっくりなめしていくので繊維がほぐれず、粘り強くて丈夫な革になるんです」 実際にピットなめしの革を長く使えば使うほど、その良さが分かってくるのだとか。丈夫で美しい、ピットなめし。  「世界でも日本でも、ビットなめしをやっているところって昔はたくさんあったらしいんですけど、 やっぱり手間と時間がかかるんで、どんどんなくなっていって。今、ビットなめしっていったら、日本だけじゃなく、世界でもかなり希少なんです」 そんな貴重なピットなめしを、中村さんは姫路にあるタンナー(製革業者)さんから仕入れています。 実際に姫路まで足を運んで話を聞き、その技術や勤勉さに惚れ込んで、ここの革を使うことに決めたそうです。 味わい深い、真鍮の魅力 製品に使われる金属パーツは、可能な限り、真鍮製のパーツにメッキをほどこさずに使用しています。 そのため、手で触れるとその水分や油分により、アンティーク風な深みを感じさせる独特の色に変化していきます。  こちらの商品は、本体の革も金具の真鍮もイイ感じの色に経年変化したもの。革も真鍮も使うほど経年変化を愉しめる素材。clife (クリフ)の商品は使えば使うほど『私だけの愛用品』へと変化していくので、愛着もひとしおです。 日常に寄りそう、clife (クリフ)のアイテム ここからは、clife (クリフ)の代表的なアイテムをご紹介しましょう。  GRASPは、シンプルなのにどこか気の利いたデザインが魅力。 カラビナのシャープなフォルムがかっこよく、他とは少し違うカラビナを探す男性からの支持が多いとか。さすが金属加工の会社ですね。 パンツのベルトループに付けても上品にまとまります。  エマージェンシーウォレットONEは、他ではなかなか見かけないユニークな形。 これは財布を考えてデザインしたというより、「お金をどう収納したら小さく持てるか」という発想から生まれたのだそう。 キャッシュレス時代の今、現金しか使えないという場面に備えるのにぴったりですね。  「財布と思って持たれると、正直ちょっと使い勝手が悪い(笑)。あくまで緊急用なんで、ギリギリ我慢できる…くらいのところを意識して作りました」と中村さん。 こうしてみると、clife (クリフ)の商品は、革を開くとひとつになる構造が多い気がしますね。 「そうですね。パーツ数を減らし、ひとつの革をたたむことによってカード入れや小銭入れを作ったりしています。シンプルを突き詰めて無駄なところなくしていった結果、『これで事足りるな』と」 いい素材を使って、シンプルに作る。 当たり前のようでいて、とても難しいことです。 「すごくハイテクな機械で製造してるわけでもないし。革のところももっと上手なメーカーさんもたくさんあるんですけど。簡単に作っているようで、ちょっとした仕立て方とか、その構造とか、デザインのまとまりとかにめちゃめちゃこだわりが詰まってる。そこに気づいてもらえたら嬉しいです」と中村さん。 clife (クリフ)が生まれる、製造現場 では、ここからは実際の製造現場を見せていただきましょう。 まずは、金属パーツを作る工場で、カラビナを作る工程を見せていただきました。  最初に、大きな1枚の板状になっている真鍮を、製品の取り分ぐらいの寸法に細長く裁断していきます。   こちらは、カラビナのパーツにあわせてカットした状態です。   先ほど裁断した真鍮を機械でプレスし、製品の形に抜いていきます。  製品を抜いたあとがこちら。 先に板に小さい穴をあけて、そこを機械にはめ込んでいきながらプレスすることで、ズレないようになっているそうです。  ちなみに、抜き終わった材料は一か所に集められスクラップ屋さんへ。 こうやって見ると、真鍮が多いですね。 「真鍮は加工しやすいし、プレスで柄も出やすい。研磨やメッキもやりやすいので、よく使われる素材です」  先ほどの型抜きでは上から圧をかけて抜くので、どうしてもカラビナの裏にあたる下側が膨らみます。 これを表も裏も同じ状態にしたいので、もう1度プレスして平らにします。  画像だと少し分かりにくいかもしれませんが、左が平らになった状態、右が平らにする前の状態です。 こうやって細部まできれいにしていくのが、こだわりのポイントですね。  このあと、ブランド名や「MADE IN JAPAN」等の文字をプレスして刻印します。 プレス作業はここで終わり、続いては研磨です。  機械の中にカラビナと石と水、洗剤のような液体を入れ、1時間半ほどぐるぐると回転させて研磨します。 機械の中にある白い物体は、大きな泡! 本当に洗濯機のようでした。  研磨したばかりのピカピカのカラビナが、画像の奥側になります。 ちなみに手前はスタッフさんの私物で、3年ほど使った状態だそう。 こうして並べると、真鍮がイイ感じに変色してるのが分かりますね。 続いては、革の裁断や縫製、組み立て作業なども見学させていただきました。    バネをつけたり、カシメを付けたりといった作業も、社内で一つ一つ丁寧に行います。  GRASPだけは、カシメを潰してフラットにしたデザインのため、圧が強めにかかる機械を使います。 カシメひとつとっても、こだわりがすごいですね。 clife (クリフ)のこだわりを、これからも 最後に今後の展開について、お二人それぞれにお伺いします。 まずは、入社10ヶ月の石原さんです。 これからどんな商品を作っていきたいか、思われてるところってありますか。 「男女関係なくどちらでも使える、ユニセックスなものとか。革製品だけでなくて、もうちょっと金属に特化したものとか。色々やってみたいですね」 石原さんは、前職が服関係のお仕事だったそうです。 「以前は、トレンドを追って勉強してるような感じだったんですけど。逆に今は、流行りのものとか、まわりの子たちが求めてるものとかを吸収して、clife (クリフ)に反映していけたらいいなと思います」  石原さんのように、客観的に見てもらえるスタッフがいると助かりますね。 「そうですね。石原さんには、主にSNS関係を任せてます。今までは、考える仕事って僕1人でやってたんですけど。そこに彼女が入ってきて、一緒にこのブランドを作っていこうとしてて。相談したことに対してわりと的確に答えてくれるんで、頼りにしてます」と中村さん。 そういう意味では、またここから変化しつつ、ブランドをしっかり伸ばしていければという感じでしょうか。 「そうですね。今までずっと、手探りで考えながらやってきたんで。これからも多分、それをずっと続けていくんでしょうけど、やっぱりブランドを成長させたいっていう欲が最近は出てきてますね」  「僕しか考えられないデザインのところは、しっかり考えて考えて。他のブランドがやらないデザインや形っていうのは、絶対外さない方がいい。そこを外しちゃうとブランドの意味がなくなってくると思うんでね」 技術としてはシンプルであっても、簡単には真似できないこだわりがぎゅっと詰まっている。 自分の持ち物にこだわりのある方には、きっと魅力を感じていただけるブランドだと思います。 宇内金属工業の皆さま、取材にご協力いただき、誠に有難うございました。 |
|

clife (クリフ)の商品一覧

カラビナキーリング | グラスプ
|

キーケース | スティル
|

カラビナ付き小銭入れ | ファウンド
|

エマージェンシーウォレット | ONE カラビナver
|

エマージェンシーウォレット | ONE キーリングver
|
|
槙田商店

|
|

|
|
1866年江戸末期に創業。織物の製造から傘の組み立てまで一貫して生産することができる、世界で唯一の老舗織物工場。私達の作る傘は、すべて織生地です。服地づくりで培われた技術と傘を組み合わせることで他にはない傘を生み出しています。日本最高峰の職人が、伝統技術をもって、「あなただけの特別な傘」を実現します。 人生を添い遂げたくなる傘をお楽しみください。 |
|

槙田商店の商品一覧
KUSU HANDMADE

|
|

|
|
「優しい」ということは、強いことでも弱いことでもなく
「優れている」ということ。古来、独特の自然香で人々を守り、
癒してくれるクスノキは、暮らしに優しい木です。 KUSU HANDMADEは九州生まれの楠(くすのき)を もっと暮らしの中へ届けるために誕生しました。 クスノキが持つ天然成分100%の防虫・消臭の力や、 安らぎの香りを是非味わってみてください。 |
|

KUSU HANDMADE 取材記
|
|
古くから「虫除けの木」として知られている楠(クスノキ)。九州など暖かい地域に自生する香木です。枝や葉から抽出された天然の「カンフル(樟脳)」は防虫や消臭の効果、リラックス効果があり、古くから防虫剤や医薬品などに使われてきました。 今回は、そんな楠の特長を生かした製品をつくるアロマ雑貨ブランド「KUSU HANDMADE(クスハンドメイド)」を展開する株式会社中村にお邪魔しました。 九州産の楠を使った暮らしに優しい製品を数々と生み出している「KUSU HANDMADE」の誕生秘話やブランドの想いを紹介します。  訪れたのは佐賀県神埼市。会社に到着して車を降りると、屋外にも関わらず心地の良い爽やかな木の香りが漂ってきました。 取材に応えてくれたのは、代表取締役社長の中村光予子さんです。 
代々受け継がれた楠で健康をつくる そもそもなぜ楠を使った製品をつくるようになったのでしょうか。歴史は中村さんの曽祖父までさかのぼります。 中村さんの曽祖父は約70年前、家具の街として知られる福岡県大川市で木材を切り出す木挽き(こびき)をしていました。「当時は、婚礼家具として楠を使ったタンスが主流だったため、ひいおじいちゃんはクスの原木を中心に切って販売していました」(中村さん)。 1974年に法人化し、時代とともに事業内容は変化しつつも一貫して楠を扱い、中村さんの父親の代からは建材を製造販売するようになりました。 ちょうど父親が建材を扱うようになった約30年前は、建築業界で木の建材から安くて施工が簡単な建材が流通するようになった時期。化学物質の影響で「シックハウス症候群」が流行していました。“健康オタク”という中村さんの父親は「建材で家も人も健康になれる。住まいから健康でなければならない」という思いから「全て天然素材を使ってお家づくりをする」というコンセプトで建材の製造販売を始めたそうです。 
「でも、実は楠は建材に向いていないんです」と中村さん。油分が多く水に強いという強みがある一方、山の中に自生することが多い楠は真っ直ぐ育たずぐねぐねと曲がりながら成長する特性があり、使える範囲がものすごく少ないそうです。そのため、たくさんの端材が出てしまうという問題がありました。 
さらに、建材としてよく使われる杉や檜と違って、曲がったり割れたりするのを防止するために人工乾燥ではなく天然乾燥をする必要があり、材料を入手しても乾燥に3-4年ほど時間がかかってしまうのです。そうなるとコストも高くかかります。 そこで端材をうまく活用できないか考えていた時、父親の知り合いから防虫剤にしてはどうかというヒントを得て、後のブランドの代表商品となるエコブロックが誕生しました。 エコブロックは切り落とされてしまう木の皮に近い耳の部分をブロックにして、天然の防虫剤や芳香剤として使うことができる商品です。香りが弱くなった時は楠から抽出されたカンフル(樟脳)オイルを塗って、繰り返し使うことができます。 
初めは父親が商品開発を進めていましたが「なんせおじさんの感性で作るのでうまくいかず…」と笑う中村さん。いくらアイディアがよくても若い人には届かなかったそうです。そこで、助けを求められた中村さんと中村さんの妹が、当時していた別の仕事をしながらも商品の販売企画に携わるようになり「KUSU HANDMADE」というブランドが誕生しました。 ちょうどメディアでは「エコ」という言葉が取り上げられはじめた時期だったため、天然の端材を活用し繰り返し使えるエコブロックはまさに環境にも人にも優しい商品として注目され、人々の手に届くようになりました。 うちにしかできない自然を使ったものづくり 一見順調に見えますが、ブランドが立ち上がるまでには大変な苦労もあったようです。 そもそもエコブロックの「エコ」は、父親が商標をとっていた「絵鼓(えこ)」という和紙壁紙から名付けられました。和紙が呼吸をすることで壁から部屋の空気を綺麗にするという商品で、何億円もの開発費をかけて開発されたそうです。 
「しかし、これが大失敗でして…」と中村さん。エコブームに乗った大手企業が後から同じような商品を販売したことで、少しでも安く手に入る大手に客が流れてしまいました。 そこで得た教訓が「大手に真似されるものを中小零細はつくってはいけない」ということ。「大手に大負けした経験から『うちが持っている楠の素材を使って誰にも真似されないものをつくろう』、そして『自然のもので人の役に立つ、繰り返し使えるものをつくろう』という思いがエコブロックの誕生につながりました」と中村さんは語ってくれました。 中村さんが社長になってからは、建材や住宅内装の事業を他社に譲渡し、現在は楠を使ったアロマ雑貨を中心に事業を展開しています。 最後まで無駄なく活用する 「KUSU HANDMADE」は九州産の楠を使った芳香や消臭グッズ以外に楠の効果を生かした掃除用品や洗濯用品、ハンガーなど生活に寄り添う商品を70種類ほど扱っています。材料となる九州産の楠は、伐採業者から捨てられるはずだったものを買い取っているため、商品のために木を切ることはありません。 
樟脳とオイルは自社独自の機械で蒸留して抽出しています。環境と人に優しいことはもちろん、「身近に使えるもの」「自分たちが買いたいもの」などを基準に社内で話し合い、年に3つほど新商品を開発しています。 
今年の2月には樟脳とオイルを抽出した後の楠チップを活用した炭の消臭アイテム「kususumi - 楠炭」が誕生。これまではスペースの問題から産業廃棄物として処理せざるを得なかった楠チップをどうにか全て活用できないか考え、独自の炭化装置を導入して100%再利用できるようになりました。 
この商品は消臭剤として使った後は土壌改良剤として再利用することができます。炭化する際に木が吸収した二酸化炭素(CO2)を炭に閉じ込めるため、そこから二度とCO2が排出されない仕組みになっており、環境に貢献できる商品です。 バイオ炭と言われるもので、バイオ炭を農地に肥料として撒くことでCO2削減につながるため、中村さんは今後バイオ炭を農家に広め、温室効果ガスの削減目標がある企業などに削減した分のCO2をクレジットとして買い取ってもらう国のJクレジット制度に活用してもらうことを目指しているそうです。そのためにも「まずは多くの人に楠炭を知ってもらうところからです」と話していました。農家にも環境にも暮らしにも役立つ商品の可能性に胸が膨らみます。 
樟脳がゼロから100になるまで ここからは、会社の敷地内にあるオリジナルの機械や作業風景を見学させてもらいました。 
まずは「KUSU HANDMADE」の看板商品である樟脳とオイルを抽出する作業場です。作業場の扉が開くと、さらに強くて優しい樟脳の香りが体を包んでくれました。 「機械は一から自分たちで考えて、機械屋さんと一緒に作りました」と中村さん。もともと他社から樟脳を購入していましたが、12年前に自社の機械を取り入れました。製造の手順が確立するまでは検証の繰り返し。蒸留時間や温度など試行錯誤を重ねながら、やっとの思いでターゲットとする成分の抽出まで辿り着くことができたそうです。ブランドを立ち上げて以降「一番大変でした」と明かしてくれました。国内で樟脳を生産する企業は4軒のみだと言われていますが、今ではこの努力があったおかげで事業が成長し、安定した生産量を保つことができるようになりました。 
中村さんが楠のチップを見せてくれました。このチップから樟脳とオイルが抽出されます。 
チップはまず独自の機械で水蒸気蒸留します。そうすると蒸気に成分が出てくるため、それを冷やすことで、冷却装に水分と固形成分(樟脳)とオイルが三層になって溜まっていくそうです。通常蒸留する時には冷却装までの間に螺旋状の管をつないで蒸気を冷やすことが多いですが、「KUSU HANDMADE」では管に樟脳が詰まらないよう、管を冷却装まで真っ直ぐつなぎ、冷却装で一気に冷やしているそうです。 
機械近くには樽に入ったカゴに真っ白な粉が溜まっていました。冷却装から取り出した水分と油分を絞る前の樟脳だそうです。樽の底には水分の上にオイルが浮いていました。樟脳は機械でプレスすることで純度100%の樟脳になります。プレスして出てきたオイルと水分は樽の底に溜まってものも含めて分離させ、オイルは製品にします。楠のチップから樟脳やオイルとして完成品になるまでは半月ほどかかるそうです。 
純度100%になった樟脳は白くて固いかたまり状になっていましたが、指で少しほぐすとサラサラの粉になりました。抽出率は多くても1%、普段は0.5~1%弱のため3kgの樟脳をとるためには少なくとも300kg分の楠が必要だということになります。市場ではいろんな樟脳が流通していますが、「ここのは間違いなく楠100%の樟脳です」と話す中村さんからは商品に対する誇りが見えました。 炭化することで環境に貢献 蒸留した後のチップを炭にするまでの過程も案内してもらいました。 
蒸留した後の楠チップは大体年間180トン出るそうですが、今までは半分を造園屋さんに販売し、残りの半分は産業廃棄物に出していました。しかし「やっぱりもったいなくって」と中村さん。場所を占領してしまうため仕方なく処分していましたが、炭にすることで100%リサイクルできるようになりました。 
炭窯も機械屋さんと相談しながらオリジナルで作ったそうです。改良に改良を重ね、現在の形に辿りつきました。会社の周辺には住宅があるため、煙も匂いも外に出ないよう機械で処理しています。 
炭にするためにはチップを溜めたバスケットを丸ごと入れて、ある程度燃え始めたら空気穴を閉じて低酸素状態で蒸し焼きにします。炭窯に入れて炭になるまでは約1日かかるそうです。空気の入れ方や火の回し方にコツがいるため、完全な炭にするのは意外と難しかったそうで、中村さんは「初めは簡単につくれるだろうと思っていたが全然簡単じゃないと嘆いていました」と笑いながら振り返ってくれました。いろんな炭の商品が出回る中で「基本的な炭の効果だけでなく、環境に寄与できるバイオ炭として差別化を図っていきたい」とのことです。 一つずつ手作業で 最後に「KUSU HANDMADE」が生まれたきっかけとなったエコブロックを包装している現場にお邪魔しました。ここではブロックの焼印や包装、オイルの充填をします。 
従業員が一つずつ手作業でペーパークッションやオイルを木箱に詰めていっていました。商品は一般販売だけでなく、結婚式の引き出物や企業のノベルティなどにも活用されています。 
特にブロックの刻印は状況に合わせてカスタマイズできるため、オリジナルの印でつくってもらうこともできます。実用的で特別感もあるため、もらったら嬉しい製品ですね! 曽祖父の代から受け継がれた楠の特徴を知り尽くし、時代を先取りしながらも原点である天然素材をフルに活用して人にも環境にも「優しい」商品をつくり続ける株式会社中村。 取材を一通り終え、中村さんからにじみ出る会社と商品への誇りがどこから来るのか感じることができました。 中村さん、株式会社中村のみなさま、長時間にわたる取材にご協力いただき、ありがとうございました! |
|

KUSU HANDMADEの商品一覧

くすのきカンフルオイル
|

くすのきエコブロック
|
|

くすのきアロマディッシュ
|

くすのき虫よけハーブスプレー
|
|

くすのきカンフルパウダー(服を守る防虫剤)
|

くすのきエアミスト
|
|

楠炭ふりふり消臭剤 kususumi
|

くすのきシャツハンガー
|
|

くすのきジャケット/コートハンガー
|
Blanc Pa(ブランパ)/大館工芸社

|
|

|
|
Blanc Pa(ブランパ) 曲げわっぱの材料の杉の外側の白い部分「シラタ」が使われず、残ってしまっていることに気づき、限りある資源である杉を余すことなく、どうにか生かしたいと試行錯誤を続けた結果、完成したのが大館工芸社のBlanc Pa(ブランパ) Blancは、フランス語で「白」を意味します。 「シラタ」への思いを「白」というブランド名に込めました。 |
|

Blanc Pa(ブランパ)/大館工芸社 取材記
|
|
木の温もりが漂うシンプルな曲線に、自然が織りなした木目がやさしく映える「曲げわっぱ」。最近は、弁当箱などを見かけることが増えましたが、実は1000年以上もの歴史をもつ日本の伝統的な工芸品です。 職人が杉の木の板から手作業で作り出す秋田県大館市の「大館曲げわっぱ」は、日本各地の曲物の中で唯一、国の伝統的工芸品に指定されています。  今回は、そんな大館市で65年間「曲げわっぱ」を作り続けてきた「大館工芸社」さんにお邪魔しました。 伝統を守りつつ、限られた資源を最大限活用しようと革新的な商品を届ける新しいブランド「Blanc Pa(ブランパ)」を立ち上げた想いも紹介します。  代表取締役の戸嶋さんにお話を伺いました。 移り変わる時代の中で求められる製品 元々は、雪国の子どもたちをイメージした三角のこけしのような民芸品や、灯篭などを作っていたという大館工芸社。紆余曲折を経て、昭和30年代から「曲げわっぱ」を作るようになりました。 地域で分業して作る会社が多い中、大館工芸社は独立して、全ての工程を自社の職人で担っています。  初めはお盆や茶筒から作り始め、次第に客の要望に応えようと弁当箱や器なども作り始めました。 見た目の美しさはもちろん、調湿効果もある「曲げわっぱ」は、時代がプラスチックに移り変わっても、「機能と見た目、両方で求められるようになってきた」と戸嶋さん。特に毎日のように使われる弁当箱は現在、大館工芸社の代表商品になりました。 
伝統と革新 一般的に「曲物」と呼ばれる「曲げわっぱ」。地域によって呼び方は違いますが、平安時代(794〜1180年)にはすでに日本各地にあったとも言われています。  戸嶋さんが、大館市で見つかった推定100年〜150年前の弁当箱のレプリカを見せてくれました。基本的な形や作り方はほとんど一緒だということに驚きです。  大館工芸社は創業以来、秋田県の高齢杉を使って伝統的な技法で製品を作り続けてきました。 通常は丸太の中心の芯と、年輪の外側の白く若い部分のシラタ(白身)をのぞいた内側の赤い部分(赤身)だけを使って、一枚の板から作られる「曲げわっぱ」。しかし、それでは貴重な高齢樹材の約半分を捨ててしまうことになっていたそうです。 大館工芸社では樹齢100年から120年の杉を仕入れて製品を作っているため、「せっかくここまで育ったのに無駄にしてしまっている」という問題意識を長年もっていました。 そこで、今まで業界では「悪くなりやすい」として使われてこなかったシラタを生かした商品を生み出しました。それらを届けるために立ち上げたのが、新しいブランド「Blanc Pa(ブランパ)」です。  均一的であることを理想とし、シラタを使うことや個性的なデザインはタブーとされてきた伝統的な「曲げわっぱ」に対して、「Blanc Pa」では、土壌によって丸太の色が違うといった自然の個性を「ポジティブに捉え」、シラタも使った商品作りを進めています。 今までは、材料の入手の難しさから「(曲げわっぱは)マーケットとしてそんなに大きく広がりようがなかった」という戸嶋さん。 しかし、シラタを含めた個性的な素材もそのまま使うことで、近年入手しづらくなっている高齢杉のロスを減らし、作れる商品の数が増えました。  新しいブランドでも、木材の伝統的な曲げ方や職人は変わりません。むしろ、これまで避けられてきた部分を使うことにより、加工の難易度は上がったそうです。常識破りな取り組みに、戸嶋さんは「チャレンジです」と語っていました。 伝統を守りながらも挑戦を続ける大館工芸社ですが、従来の「曲げわっぱ」でも、新しいブランドでも共通する想いは「いいものを長く使ってもらいたい」ということでした。 そのため、どちらの商品も「リペア(修理)に力を入れている」と戸嶋さん。汚れや傷、欠けなど、できる限りリペアの対応を受け付けています。  ところで、「Blanc Pa」の由来はなんでしょう。 「Blanc(ブラン)はフランス語の「白」、Pa(パ)は「曲げわっぱ」の「ぱ」で、二つを合わせた造語」(戸嶋さん)だそうです。 ブランドは地元のデザイナーと手を組んで作り上げています。ここにも、大館工芸社の地元へのこだわりが見えました。 新しいブランドでは、若者や男性などターゲット層も広がっています。新しい商品の構想がどんどん練られているという「Blanc Pa」。ますます目が離せません。 杉へのこだわり 日本各地の工芸では、少子高齢化などによる後継者不足が問題になっていますが、戸嶋さんはこの業界の1番の課題を「材料の確保」だと語ります。杉の木は日本で多く植林されているのに、なぜでしょうか。  大館工芸社は創業当時から秋田県の杉の木にこだわってきました。なぜなら、日照時間や天候によって、年輪の幅が変わるためです。 生産量が全国一の宮崎県の杉の木は日に当たる時間が長く、秋田県の杉の木と比べて成長スピードが2倍ほど違うようですが、成長が早い分、年輪が広くなります。それに対して、「秋田、東北では厳しい寒さが続き、晴れる日が少ないことによって木の成長が遅く、(年輪が)ぎゅっとつまります」(戸嶋さん)。  「曲げわっぱ」に映える、細かく美しい木目は秋田県の杉の木ならではのものだったのですね。 確かに、その中で樹齢100年から120年ほどの木となると、かなり限られます。もう少し樹齢が若い木は使わないのでしょうか。  「曲げわっぱ」は丸太を縦に切った木の板から作りますが、丸太が太ければ太いほど幅の広い木材が取れるため、高さのある「曲げわっぱ」の製品を作ることができるそうです。 戸嶋さんは木材を示しながら、樹齢80年の杉でさえも「十分な高さが取れない」と教えてくれました。 長い年月がかかった自然の結晶に、職人の手の技が加わるからこそ、価値があるのだと感じました。 全ての工程を手作業で ここからは曲げわっぱが製造されている工場にお邪魔してみましょう。  工場に足を踏み入れると、木材を機械で切る音が響いてきました。普段は30人ほどで役割分担しながら作業しているそうです。  湯気がたちのぼるエリアに近づくと、何枚にも重なる木材が、お風呂に入るようにお湯に浸かっていました。“湯船”の下では火が焚かれ、なかなかインパクトのある光景です。 これは、木材を曲げやすくするために90度ぐらいのお湯に1、2時間程度つけておく工程だそうです。   型と留め具が並んでいました。そして隣の台では、これらを使って固定された製作途中の弁当箱が並んでいました。 どのようにしてこの状態になるのでしょうか。実際に職人が曲げる場面を見せてもらいました。  お湯から取り出したばかりの湯気を立てている板を難なく触り、丁寧に手で包み込むように型に沿わせ、留め具をはめていきます。板の熱さを感じさせない無駄のない動きは、まさに職人技でした。 また、曲げた部分を接着する場面も案内してもらいました。こちらは企業秘密のため撮影NGです。桜皮で留めるスタイルは江戸時代から変わらないそうです。濃い茶色がパッキリと映えて、デザイン性もありました。 こちらは、大館工芸社で「伝統工芸士」という資格をもつ5人のうちの1人が作業をしていました。    その後、隙間がないよう底をはめ込み、丁寧に磨いて形を整えます。 仕上げはウレタン塗装です。 油物にも耐えられるよう塗っていきます。厚く塗りすぎても調湿効果の機能に蓋をしてしまい、薄すぎてもウレタンの効果が薄くなってしまうため、これも職人技です。網の目状に塗装して、除湿効果を保っているそうです。 一通り工程を見ましたが、実は板を曲げて形を作った後にかかる時間の方が長いことがわかりました。全てに共通することは、手作業でかなり手が込んだ作業であることです。  最後に商品が陳列されたスペースに戻ってきました。 床に使われている木材は、「曲げわっぱ」に使われなかった芯材。そして、製品が並ぶ台は樹齢250年の丸太。 解説を聞いた後だからか、上に並ぶ製品も含めて改めて見ると、長い年月を経てきた重みや、職人の変わらぬ技と想いがますます鮮明に伝わってきました。 戸嶋さん、大館工芸社のみなさま、長時間にわたる取材にご協力いただき、ありがとうございました! |
|

Blanc Pa(ブランパ)の商品一覧

秋田杉の曲げわっぱ カップ
|

秋田杉の曲げわっぱ ディッシュ
|
|

秋田杉の曲げわっぱ ボウル
|
人水 / JINSUI

|
|

|
|
JINSUIは日本一の常滑焼の急須の産地と知られる愛知県常滑市にございます。 品質が非常に高く、最高峰の急須を作っている産地の一つです。 職人の世界では、お茶を愉しむ時間の事を「時わすれ」と表現します。 そんな特別な「時」を楽しんで欲しいと願いを込めて急須。 江戸時代に創業し、常滑の良質な土と巧みな技術を現代まで受け継いできたJINSUIの新しい物づくりが此処にあります。 |
|

JINSUI / 人水 取材記
|
|
急須の生産量日本一、国内シェア9割を誇るのは愛知県常滑(とこなめ)市。  知多半島の中部西岸に位置する海と山に囲まれた自然豊かな街で、人気の観光スポット「やきもの散歩道」は、「美しい日本の歴史的風土準100選」にも選ばれています。  そして、常滑市の伝統工芸品「常滑焼」は、瀬戸、信楽、越前、丹波、備前と並ぶ「日本六古窯」に数えられる由緒ある焼き物で、「日本六古窯」は、2017年に文化庁が日本遺産(※)に認定されています。「日本六古窯」の中でも「常滑焼」の歴史はもっとも古く、1200年以上も前の平安時代まで遡るのだそう。  今回は、そんな歴史ある常滑焼の急須を作る「株式会社人水(JINSUI)」の社長 渡邉さんに話を聞きに行ってきました。ブランドを代表するオリジナル急須「TOKI」シリーズは、強さと繊細さを兼ね備え、凛とした空気を纏う美しい逸品です。  この取材を通して、常滑焼の急須に興味がわき、急須でお茶を飲んでみようと思っていただけたら嬉しいです。 ※「日本遺産(Japan Heritage)」は地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するものです。ストーリーを語る上で欠かせない魅力溢れる有形や無形の様々な文化財群を,地域が主体となって総合的に整備・活用し,国内だけでなく海外へも戦略的に発信していくことにより,地域の活性化を図ることを目的としています。 独特な朱色が魅力の常滑焼 市内の人気観光スポット「やきもの散歩道」には、煙突や窯、工場などが点在。焼き物の壁や道が広がり、何とも不思議な景色を楽しむことができます。さらに、陶芸家の作品として招き猫が街のあちこちに展示され、焼き物コレクターはもちろん、写真愛好家や映えスポットとして若い世代の方からの人気も高まっています。   そんな常滑市の伝統工芸品が、独特な朱色が特徴の「常滑焼」。鉄分が多い陶土を使用することで、特有の朱色に焼き上がるのだそう。大きな壺や瓶、植木鉢なども生産されていますが、代表する製品と言えば急須。  お茶を飲むために使う急須はお湯を注ぐため、無意識に深さや軽さを求め、形やデザインは、どの産地、どのブランドでも大きな差がない。そんな印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 こうした代わり映えしない急須のデザインに一石を投じたのが、今回取材させていただいた株式会社人水(JINSUI)です。JINSUI「TOKI」シリーズの急須は、長い歴史で培われた使いやすさに加えて、現代の住空間や生活雑貨のトレンドに合うスタイリッシュさ、茶葉の広がり方、つまり、美味しいお茶の抽出まで考慮された、革新的なデザインが魅力です。 
時と急須。時計とデザイン 「TOKI」シリーズは、株式会社人水(JINSUI)の渡邉さんが感性で作った急須で、時計の針をモチーフにした平たい形が特長です。カラーも、KINARI(木成り)・SHIROHAI(グレー)・SUMIKURO(墨黒)が展開されています。  「健康志向というのもあり、緑茶はクローズアップされていますよね。緑茶と急須はセット、日本の文化として急須を世界に提案したい。そして、伝統を現代に伝える手段として、今までの“THE急須”と差別化できる急須を作りたいと思い、取っ手と注ぎ口を秒針と分針に見立ててデザインした、“TOKI”を考えました。職人の世界では、茶を愉しむ時間のことを“時わすれ”と言い、時を忘れ、茶を飲み、そして、時を思い出す。そんな“時”を愉しんでほしいという想いを込めています」と、渡邉さん。  さらに、「平たいデザインにすることで茶葉が広がりやすく、陶製の茶こしの見た目は高級感もある。最近のインテリアに合わせてグレーも販売しています。釉薬を使っていないグレーはJINSUIだけだと思う」と、オリジナルシリーズ誕生の経緯とこだわりを教えてくれました。 クオリティに自信あり。象徴的な陶器の茶こし 「海外の人からは、“日本の物は長く使えるよね”と言ってもらえることがあり、この認識を薄めてはいけないと思っている」と、品質にも徹底的にこだわっている渡邉さん。 JINSUIの急須には、本体と一体化した陶器の茶こしがついているのですが、これを作る作業は実に複雑。渡邉さんも「他社で陶製の茶こし付きの急須は量産できません。品質の基準を満たさないものはすべて破棄している」と話し、作り手の技術への自信と品質を維持するためのこだわりが、ひしひしと伝わってきました。  JINSUIには「TOKI」の他にも、“THE急須”のサイズ感やデザイン、機能を活かしながらアレンジしたオリジナルシリーズ「IROIRO」があります。  このようなさまざまなデザインの急須を、何と1ヵ月で6,000個も作ることができるのだそう。  急須は、茶こし、取っ手、注ぎ口、蓋、つまみ、胴体と言われるパーツがあり、それぞれを成形した後に接合していきます。  さらに、常滑焼には、胴体と蓋をしっかり密着させるための蓋擦りという特徴的な工程があります。この複雑な工程は機械ではなく、すべて手作業で行われていることに驚くと同時に、しっかりとした生産体制が組まれていることに凄みを感じました。 創業は江戸時代。変化しながら成長して200年 常滑焼の伝統を守りながら、新たなことにチャレンジする渡邉さんは、実にユニークなキャリアの持ち主です。 「中学3年生の頃から服が好きでリメイクするようになり、ファッションの学校へ。その後、花に興味を持って1年間学校に行って、花の装飾を専門にする花屋を始めました。2006年頃ですが、飛び込み営業をしていましたね。服や髪型と同じように、“バランスを見ながらコーディネートします”というスタイルで、結婚式場から仕事をもらったり。ただ、当時は個人事業主では信頼してもらえない時代で難しかった」と、渡邉さん自身が歩んできた道を振り返ってくれました。  さまざまなバイトをしながら生計を立てて過ごす中、父親が守ってきた釜屋「人水陶苑」を受け継ぐことになったのは、渡邉さんの転機と言えるのではないでしょうか。 「はっきりしたことは調べられていないのですが、江戸時代の1800年頃に釜屋として創業。ずっと焼き物というカテゴリーでしたが、祖父の代から人水陶苑(じんすいそうえん)として急須作りを始めたんです。そして2014年、代替わりのタイミングで法人化し、株式会社人水(じんすい)になりました」と教えてくれました。  200年以上の歴史の中で、生業を陶器を焼くことから急須を作ることへ。そして今、さらなる進化としてオリジナルの急須を作りながら、現代に合わせたデザインと売り方へ大きく舵を切ろうとしています。 古い考えが衰退の理由。何を言われようと突き進む 現在、渡邉さんはデザイナー、営業責任者、経営者の三刀流でフル稼働。急須をより魅力的な物にしたい、もっとたくさんの人に届けたいという強い想いを胸に、改革者としていばらの道を歩まれています。 「今まで、常滑焼きは地場の問屋さんにしか出せなかったんです。変なところに並べられたり、値段も安くつけられたりして、製造する側は儲からなかった。そこで、2年前ぐらいから問屋に卸すのをやめて、自分で販売ルートを作り始めました」と渡邉さん。今まで培ってきたものを壊してでも、変えなければならない! という強い信念を持って動き始めました。  日本では卸売業が発達し、社会や生活を支えてきました。しかし、交通網が整備されインターネットが普及する中で買い物のスタイルは大きく変化し、大量生産・低価格の物が溢れ、手作りの価値がないがしろにされてきたと言っても過言ではありません。 「陶磁器のコーディネーターさんが“JINSUIを紹介してください”と言ったら、問屋さんから“紹介できない”と言われ、直接連絡が来たことがあるんです。どうやら、常滑焼の歴史が始まって以来のワルって言われているそうです。でも、儲からないことはやらない。悪名無名に勝るっていうテーマでやってます(笑)。問屋さんの中でも価格が合ったら全力でやりますし、納期も絶対に守りますよ」と、苦労しながらも前に突き進む渡邉さんの姿に感動しました。 
急須でお茶を飲む。日本の文化を世界へ! 「TOKIシリーズには急須作りの技術を活かしたランプシェードがあります。誰にも真似できないものを作ってみようという思いからで、ラインがすごく綺麗なんです」と渡邉さん。これは、食器というカテゴリ以外から急須にたどり着いてもらうための策であり、日本国内だけでなく、お茶を飲む文化のない世界の人に知ってもらうためのアイディアです。  他にも、贈り物や生活雑貨の見本市、ギフトショーにも出展するなど挑戦を続けられています。こうした販路の拡大は、売上や経営に直結するだけでなく、ブランドや産業の成長には不可欠と言えるのではないでしょうか。 「僕は、仕事は待つんじゃなくて“迎えに行く”と表現しています。作るのに追われて外に出れないという話は聞きますが、デザインも営業も社長業も、新しいことを始めるための時間を作り行動しています。誰かに評価してもらえた時は嬉しいですが、それを求めて動くって変だなと思っていて、自分を肯定する、自分を評価できるのは自分しかいないと」と、仕事の流儀も教えてくれました。  また、「仕事を見て、すごく楽しそうで良い生活しているって思ってもらいたい」と話し、技術を育てることはもちろん、働きたいと思ってもらえる職場環境作りにも全力で取り組んでいることを感じることができました。そして、渡邉さんは「6,000個くださいと言われて、“はい、できますよ!もっとできますよ!”と返事をしたい」「商品を見てもらって、どこに出しても恥ずかしくないものを作る」「急須と言ったらJINSUIというポジションを掴みたい」と目標を語ってくれました。  高品質な急須作りへのこだわり、日本の文化として急須を世界に届けたいという強い想いが感じられる取材でした。 印象としては、デザイナー、アーティストのような側面をお持ちの渡邉さん。目指すところに進むパワー・推進力、そしてブレない軸、話しているとぐいぐい引き込まれるような魅力をお持ちの職人さん。 だからでしょうか、JINSUIの商品からは、渡邉さんのこだわりとものづくりの魅力が漂うような、引き込まれる印象を受けます。 これからますます沢山の、ものづくりの魅力を漂わせた素敵な商品を生み出されるのだと感じています。今後もとても楽しみな職人さん、ブランドです。 急須でお茶を飲むのは日本の文化。ぜひ、日本の茶葉とJINSUIの急須でお茶を飲んでみてください。 渡邉さん、JINSUIの皆さま、取材のご協力誠に有難うございました。 |
|

JINSUIの商品一覧

常滑焼の急須 | TOKI
|

常滑焼の植木鉢 | TOKI PLANT
|
|

常滑焼の急須 | IROIRO 01
|

常滑焼の急須 | IROIRO 02、03
|
|

常滑焼の保存容器 | IROIRO
|
|
吉田ヤスリ / YOSHIDA YASURI

|
|

|
|
吉田ヤスリ製作所は、新潟県燕市にある、創業から100年以上金属加工技術を受け継いでいる製作所です。職人が手作業で一つ一つやすり目を打ち込んでいるシンプルかつ高品質な爪やすりを製造しています。 |
|

吉田ヤスリ / YOSHIDA YASURI 取材記
|
|
日本有数の金属加工の町として知られる新潟県燕市。 燕市の地場産業は、江戸時代初期に日本家屋に使われる和釘作りに始まり、その製造で一大産地となりました。 和釘作りで培われた金属加工技術は、その後ヤスリや銅器、キセルなどの日用生活品にも波及していきます。これらの技術は職人たちによって現在に至るまで脈々と受け継がれて発展を遂げ、”Made in TSUBAME"は全国的にも有名になりました。 またこの地域の産業は独特で、金属加工におけるプレス、磨き、研磨、洗いなどの各工程が専門化された分業制が確立されています。  今回のインタビューでは、その中でも特に珍しいヤスリの「目立て」を専門とする吉田ヤスリ製作所にお邪魔しました。 爪やすりとは? 吉田ヤスリ製作所が手がけるのは、爪やすり。やすりというと工業用のものや、ペーパーやすりなど思い浮かべる方もいるかもしれませんが、吉田ヤスリ製作所では爪のやすりのみを手がけているプロフェッショナル。 爪やすり、みなさん馴染みはあるでしょうか? 吉田ヤスリ製作所で爪やすり紹介動画を作られています。よければご覧ください。 いかがですか。馴染みのある方、ない方、いると思います。 恥ずかしながら、私も最初は爪やすりは爪切りで爪を切った後に整えるものだと思っていました。 そうではなく、爪切りをせずに、やすりで削るための道具を爪やすりと言っています。爪を切るのではなくやすることで、爪が繊細で爪切りに悩みを持っている方の問題が解決します。 詳細は商品ページでご覧ください。 そんな爪やすりの専門メーカーが手がける「爪やすり」にはどのような特徴があるのでしょうか? 熟練の技が光る「目立て」とは  爪ヤスリの素材に使われているのは、約1㎜の薄いステンレス板です。 このステンレス板に「たがね」と呼ばれる鋼を打ち込み、ヤスリの目を立てていく工程を「目立て」と言います。  ↑こちらがたがね 吉田ヤスリ製作所では、目立て機を使ってたがねの刃を等間隔に打ち込み、全て手作業で目立てを行っているのですが、たがねが水平に研げていなかったり、目立て機の強弱のバランスが狂うと、ヤスリ目は均等に仕上がりません。  目や耳、手先の感覚を研ぎ澄ませ、目立て機の振動やヤスリ目の微妙な触感の違いを感じ取って進めるこの工程。これは長年の経験によって初めて成し遂げられるものなのです。 熟練の職人により等間隔に整然と打ち込まれたヤスリ目は、見た目も美しく、使い心地も抜群です。 「YOSHIDA YASHURI」ブランドの爪やすり 吉田ヤスリ製作所は明治後期に創業し、鉄をはじめとする工業用ヤスリの製造を行っていました。昭和30年には爪やすりの製造を開始し、昭和44年に有限会社として設立。以来、長年にわたりその技術を継承し続けています。  創業から120年以上の歴史を持つ吉田ヤスリがこだわるのは、線ではなく“点”で削るという考え方です。通常の爪ヤスリは一方向にのみヤスリ目が入っていますが、吉田ヤスリの爪ヤスリでは、左右斜め方向と水平方向の三方向にやすり目が入れられています。  3段の目が交差して点を生み、その点が爪の細かな繊維をしっかりとキャッチするため、爪が逃げずにヤスリ面に沿い、負担をかけずに滑らかに削ることができるのです。 オリジナルブランド「YOSHIDA YASURI」では、この伝統の技術をそのままに、使う人の用途に応じた、誰もが使いやすい爪ヤスリを作ることを目指しています。 燕市の地場産業の変遷  現在でも多くの人から愛される「YOSHIDA YASURI」ですが、燕三条の地場産業は戦争を経て大きく変化してきたといいます。その流れついてお聞きしました。 「戦前はこの地域に鉄ヤスリ屋が100社程あり、最盛期の昭和12年頃には一年間に4000万本も作られていました。満州事変や支那事変などで軍事需要が大きくなり、燕市だけで業者100 社、従業員も600 人以上いたと聞いています。しかし戦争が終わると同時に需要が急減し廃棄したところも多いんです。」  「その時にうちは鉄ヤスリから爪ヤスリに転換しましたが、現在、燕で同じ爪ヤスリを作る会社はもう1社、工業用のヤスリを作るところがもう1社だけです。全国的に見ても非常に少ないです。」  そう教えてくれたのは7代目の吉田実さん。戦争の終結による鉄ヤスリの需要縮小にさらなる追い打ちをかけたのが、技術の発展だといいます。 それまで金型の仕上げには必ず鉄ヤスリが必要でしたが、金属加工の技術の発展により鉄ヤスリでの工程が減り、需要が減っていったそうです。 現在の生産体制と課題 では、現在の生産体制はどうなっているのでしょうか。職人さんたちの人数についてもお聞きしました。 「 昔は半分手仕事で、職人さんもたくさんいました。今は私と父、外の職人さんが2人か3人いるくらいです。忙しい時は外注も使いますが、中国への輸出が多かった90年代が一番多忙でしたね。」  海外にも輸出しているということですが、同じような技術や物は海外にもあるのでしょうか。 「ヨーロッパやアメリカにもありますが、爪ヤスリに特化しているところは少ないです。また日本の製品は質が高いと評価されています。」  そう話す実さん。国内でのEC販売をメインに行いつつアメリカやカナダの小売店への定期的な出荷もするなど幅広く手掛けているそうです。 OEMとオリジナル製品のバランス 先代の社長の時代には他社ブランドの製品の製造を受注するOEMでの販売を中心に行っていたそうですが、現在8代目の社長を務めている尚史さんが会社に入ってからはオリジナル製品を作り始めたそうです。  オリジナル製品の製作を始めたきっかけは何だったのでしょうか。 「他に真似できないステンレス製爪ヤスリの目立ての技術を集約させた、吉田ヤスリ製作所の名を冠したオリジナルの爪ヤスリを作らなければならない、という思いはずっとありました。 しかし自社でつくり、そして自社で売るところまでをパッケージ化して、経営していくためにはどうしても時間が足りず、後回しになってしまっていたんです。 そんな中、息子が家業に入ったことで時間的な余裕も生まれ、オリジナル製品に取り組むことが出来るようになりました。」  それがオリジナルブランド「YOSHIDA YASURI」の始まりなんですね。現在はどのような割合で製作を行っているのでしょうか。 「コロナ禍の影響でOEMが落ち込んだ時期がありました。その時、ECサイトでの販売に助けられた経験を活かし、オリジナル商品の制作に取り掛かりました。今ではOEMとオリジナルの比率がちょうど半々くらいになっています。 表面の傷取りをしてロゴを入れ、自社ブランドとしての価値を確立させています。『良いものを作っていれば、大丈夫!』という思いで、自社ブランドとしての販売に挑戦しています。」 そう話す実さんの表情からは、自社ブランドへの自信が伝わってきます。 後継者としての思い  現在8代目の社長を勤めている尚史さんですが、家業を継ぐことに関してはいつから決めていたのでしょうか。後継者としての思いについてもお聞きしました。 「実は30歳までは全く別の仕事をしていました。会社員として医療福祉関係の仕事をしていて、当初はいずれ家業を継ぐなんてことは考えたこともありませんでした」 そう話す尚史さん。実家の工場を継ぐと決めたのは、尚史さんの父であり7代目の社長である実さんが60歳になった時のことだそうです。 「先代の社長から後継者になってほしいと言われたことはなかったのですが、大変な時期も見ていましたので、工場を継ぐことを考えるようになりました。 また父が60歳になったのも一つのきっかけで、元気なうちに技術を学びたいということもあり決断をしました」 尚史さんの表情からは家業と地元のものづくりを支えていく覚悟が感じられました。 今後の展望  大変な時期のものづくりを見て家業を継ぐことを考えたという尚史さんですが、これまでにどのような苦労があったのでしょうか。 「コロナの影響も相当大きかったのですが、20年前のサブプライムローン危機の時期が一番きつかったですね。国内の需要がかなり冷え込んで、売上は半減してしまいました」 ではそんな時期をどう乗り越えていったのでしょうか。 「受注が減ってしまった時期に、楽天市場と自社のECサイトを始めたんです。その頃からインターネットでの販売を広げていったことで、コロナ禍でもなんとか乗り越えることができました。 また、多くのお客様から高い評価を頂くことができ、大変嬉しく思っています。レビューに加え、さまざまなご意見を直接伺うことができますので、それらを製品開発に活かしていきたいと考えています。今後も使ってくださる方々の姿をしっかりとイメージしながら、自社製品の開発と販売に一層力を注いでいきたいと思います。」 と今後の展望についても話してくださいました。 吉田ヤスリ製作所のお二人も、また燕三条地域の他の職人たちも、時代の変化に柔軟に対応しながら伝統の技術を守り続けています。 彼らの努力と情熱がこれから先も、この町のものづくりを支えていくのだと感じました。吉田さん、ありがとうございました。 |
|

吉田ヤスリの商品一覧

ステンレス製 爪やすり
|

ステンレス爪やすり こども用
|

ステンレス爪やすり ペット用
|
深海産業(Broom Craft)

|
|

|
|
Broom Craft 歴史ある箒の作り方をもとに、スタッフによって新たに生み出された独自の製法を加え、職人がひとつひとつ手作りで製作しております。 棕櫚・シダ箒の持つ深い歴史を、人の手で大切に繋いでいきたい。 未来に、そして世界へ。 そんな想いを胸に、日々丁寧に心を込めて、物づくりと向き合っています。 |
|

深海産業(Broom Craft)取材記
|
|
青く晴れ渡る空に、緑豊かな山々、広がる田んぼ。 今回の取材記では、日本の原風景のような景色が広がる和歌山県海南市にやってきました。  和歌山を代表する特産品といえば、みなさん何を思い浮かべますか? パッと思いつくところでいえば、梅のトップブランド「南高梅」や、甘くてジューシーな「みかん」でしょうか。 ですが、和歌山にはまだまだ隠れた特産品があります。それが、今回お邪魔した「深海(ふかみ)産業」さんの手がける棕櫚(しゅろ)製品です。 棕櫚という言葉、初めて聞いたという方もいらっしゃると思います。 棕櫚とは、いわゆる「ヤシの木」に似た木の一種。私たちが暮らしの中で目にするものでいえば、箒(ほうき)の穂先やタワシなどに使われる素材です。 深海産業では、そんな棕櫚の歴史を未来に繋いでいこうと、オリジナルブランド「Broom Craft(ブルームクラフト)」を立ち上げ、さまざまな商品を制作しています。  こちらは看板商品の国産棕櫚箒。サイドにほどこされた三つ編みがトレードマークです。耐久性が高く、丁寧にお手入れすれば20年30年と長く使用することができます。   その他、フライパンにこびりついた油汚れを落とすのに便利なキッチンブラシや、気になるところが手軽に掃除できる手帚など、ラインナップも豊富。 今回の取材記では、聞き慣れない棕櫚という素材についてはもちろん、深海産業が作る箒の制作秘話から製造現場の様子まで、たっぷりお届けします。 この取材記を通して、みなさんが棕櫚という素材を知り、箒をもっと身近に感じていただければ嬉しいです。 棕櫚って、なに? 「Broom Craft」が手がける棕櫚の箒は、しなやかで柔らかい掃き心地が特長。 また、繊維に適度に油分が含まれているので、埃を舞い上げずに掃くことができ、畳やフローリングに艶が出てくるワックス効果もあるとか! 知れば知るほど箒の素材として優秀な棕櫚ですが、そもそもどういった植物なのか、詳しく教えていただきましょう。お話をお伺いしたのは、スタッフの津村 昴さんです。  はじめに、加工する前の棕櫚を見せていただきました。棕櫚は、木の幹を覆っている皮の部分を製品に使用します。  まるで人が織ったかのように、格子状になっていますね。これがまったく人の手が加わっていない“自然の状態”というから驚きです! 「もともとこのあたりの山には、棕櫚の木がたくさん自生しています。一説には、高野山の弘法大師・空海さんが『これは産業になる』と言って広めたとも伝えられているんですよ」と津村さん。 時代とともに移り変わる、棕櫚の今 ここまで話を聞くと、地元に生えている棕櫚を使って箒を製造しているのかと思いますが、現在、素材の棕櫚自体は中国から輸入しているそうです。 なぜ国内に生えているのに、わざわざ輸入するんでしょうか?  「昔はこのあたりに生えている棕櫚を原料にして箒やタワシを作る地場産業が盛んだったのですが、時代とともにだんだんと下火になっていきました。今ではそのほとんどが、スポンジや歯ブラシといった家庭用品を取り扱う会社に変わっています。今の日本では、棕櫚の木が生えていても、その皮を剥ぐ人がほとんどいない状況です」  そもそも棕櫚の木というのは、皮を剥がされると、より強くなろうとしてどんどん硬い皮を生み出す性質があるそうです。人間の皮膚も、外部から刺激を受けると皮が厚くなったり、硬くなったりしますが、まさにそれと同じ。 逆にいうと、皮を剥がないと皮はやわらかいまま。せっかく棕櫚の木があっても、皮を剥いで手入れする人がいない今の日本では、やわらかい皮しかとれません。 「そのやわらかさを生かして、今でも一部のタワシ作りには使われているようですが、ふにゃふにゃし過ぎて箒作りには向いてないんです。なので、うちは棕櫚の素材に関しては中国に頼っています。中国の方が圧倒的に質が良いんですよ」と津村さん。 未来を見据えて始めた、箒作り もともと深海産業は、1950年頃に先代の深海 洋治さんが自宅で棕櫚縄の生産を開始したのがはじまり。それ以来、70年以上にわたって棕櫚縄を製造し続けてきました。 棕櫚縄は、主に緑化資材として活用されています。 例えば、街路樹が倒れないように添え木をあてて結ぶのに使ったり、竹垣の竹を組むのに使ったり。最終的には自然に還るエコな素材として重宝されており、深海産業が日本国内で95%のシェアをもつそう。  「ですが、なかなか時代の流れもあって、棕櫚縄だけではいけない、と。なにかしようというところで始めたのが箒作りなんです」 それが2019年のこと。会社としては歴史ある深海産業ですが、箒作りに関していえば、まだまだ歩き始めたばかりなのです。 きっかけは、京都からの依頼 では、箒を作ろうと思った最初のきっかけはなんだったのでしょうか。当時の事情を、専務取締役の深海 耕司さんに聞きました。 「僕が各地の職人さんを訪ねて回っていたときに、京都の荒物を取り扱う商店の女将さんから依頼を受けたんですよ。京都のシダ帚を作る職人さんがいなくなってしまい、このままでは伝統が途絶えてしまう。なんとかしてシダ帚を復活させてくれないかって」  シダとは、パルミラという木の葉柄部分(葉を支える枝の部分)から取り出す繊維のこと。京都ではこのシダを使った箒が昔から使われ、「京帚」や「庭帚」などと呼ばれていました。 棕櫚とシダは似た素材なので、棕櫚縄を扱う深海産業ならなんとかできるのではないかと女将さんは考えたのでしょう。 「いただいた箒を解体して、職人みんなで研究し、なんとか納品はできたんですが。やはり箒に関しては素人なんで、クレームが発生してしまいました」 クレームから生まれた、独自の製法 クレームの内容は、「帚の毛が抜ける」というもの。いきなり大きな難題にぶつかった深海産業ですが、ここから本領を発揮していきます。 「僕らはいい意味で全員が素人のところからスタートしたんで、変な固定概念がないんですよ。今まではこうして作っていた、こうしなければいけないっていうのが、何もなかったので。純粋に『どうすればよくなるか』だけを突き詰めて考えました」と深海さん。 「なぜそういうことが起こるのか」「どうしたらいいのか」。職人が一丸となって問題と向き合い、解決策を徹底的に考えました。そうして生み出されたのが、毛を抜けにくくする独自の製法です。  もともと箒は、毛をまとめた束(これを玉と呼びます)を合体させてできています。 画像の「従来」と書いてある玉が、伝統的な製法で作ったものです。芯に対して毛を巻きつけるだけですので、使い続けるうちに毛が抜けてしまうことがありました。 画像の「新規」と書いてある玉が、深海産業独自の製法で作ったものです。今までとは倍の長さの毛を用意し、芯に巻きつけてから折り返して銅線で留め、その上にさらに毛を足す。そうすることで、従来よりも毛が抜けにくい仕様となりました。 もちろん、今までより時間も手間もかかりますが、使い心地を一番に追求するからこそ考えつくことができた製法です。 トレードマークとなる、三つ編みの誕生 京都の伝統製法に独自の製法を加え、シダ帚を見事に復活させた深海産業。そのノウハウを生かして棕櫚箒の制作にも取り掛かりますが、こちらでも、また難題にぶつかりました。 それが、箒を使うときに最も力が掛かるサイド部分の「強度」です。一般的な棕櫚の箒はこの部分に銅線を巻くことが多いのですが、使い続けるうちに銅線が切れたり、ゆるんだりしてしまいます。 銅線を巻かずに、強度を保つ方法はないか。それを突き詰めた結果生まれたのが、商品名にもなっている三つ編み(TRECCIA)。棕櫚をぎゅっと編み込むことで強度をキープしつつ、見た目にもオシャレな佇まいに仕上がりました。  「うちは女性の職人が4人おりまして、女性からの意見も取り入れています。…でも正直言って、最初僕は大反対したんですよ」と笑う深海さん。 「そもそも僕は三つ編み自体やったことがないので、それを棕櫚でするっていう発想がなくて。三つ編みだと、可愛すぎるんじゃないかと思ったんです。今は、うちしかやっていない製法ですし、特に女性の方に可愛いとご好評いただけて良かったな~と(笑)」 伝統を守りつつ、進化していく 「うち独自の製法で箒を作っているので、本当に“伝統工芸”かっていわれると、どうなんだろうと思う部分もありますけど…」 伝統をそのまま受け継いでいくことももちろん大切ですが、深海産業は問題を問題のままにせず、時代に即して、より快適な使い心地に進化させていくスタンスをとっています。  「見た目は伝統に則った形で、使い勝手としては従来の物よりいいものを、ということで常にアップデートできるようにしています」と深海さん。 進化を続ける一方、伝統を守りたいという想いから、深海産業では“職人育成プロジェクト”に取り組んでいます。これは、年齢・性別・経験の有無を問わず、箒作りのノウハウを伝えていく仕組み。 「職人さんが技術を止めてしまって、弟子にしか教えないというのでは、伝統が止まってしまう。誰でも作れるような工程でカリキュラムを組み、『ここ、こうしたらやりやすかったよ』とか、社内で情報共有しながら箒作りができるようにしています」と津村さん。  箒作りに限らず伝統的な物作り全般に言えることですが、おじいちゃんが一人でやっていて、誰も後を継がないということがよくあります。現に京都のシダ帚も、そうやって一度途絶えてしまいました。こういったことがまた起こるのを防ぐ、画期的な取り組みですね。 生き生きとした、楽しい制作現場 ここからは、箒の制作現場にお邪魔します。 箒という商品から、いわゆる職人気質的な空気感をイメージしていましたが、いい意味で裏切られました。性別も年齢も社歴も関係なく、和気あいあいとした楽しい雰囲気があふれています。  「みなさん家庭もあるし、子どももいるんで。例えば今日は風邪を引いたからって急に休んだり早退してもOKです。やっぱりそういう働き方をしたほうがいいですよね」  「商品を作るっていうのは反復作業なんで、しんどい部分もある。ゆとりを持ちながらやるっていうのが大事です」と深海さん。その言葉通り、工房内は楽しい会話が飛び交います。そうやってワイワイ話をしつつも、作業する手は少しも止まらないのがすごいところです。  「僕らは職人のイメージっていうものを払拭したいんですよ。箒だけじゃなくて、どの業界もそうだと思うんですけど、職人が少なくて若い人がやりたくないっていう背景には、『難しそう』とか、『職場の環境が悪そう』とか、そういうイメージがあるんだと思います」と深海さん。  「うちは見ての通り、堅物に取り組んでるっていうわけでもなく、楽しくやっています。もちろん、『楽しく』の中でも、きっちりやるところはやりますよ。お客様にちゃんとした商品を届けたいんでね」  こちらは、棕櫚箒の三つ編みをしているところです。髪の毛をおさげに編んでいるような感じですね。「髪の毛を編むときとは、ちょっと力の掛け方が違います。上に向けて力を掛けていく感じ」と職人さん。  三つ編みの数や長さなどは、特に決まってないそうです。 「玉を合体させて組んでいくときに、一度編んだものをほどいて調整したりするので、作ってみないと分かりません。なので、箒の一本一本が、本当に世界にひとつだけなんですよ」  こちらでは、箒の玉を作っています。ある程度大きさを揃えて個体差が出ないようにするため、同じ職人さんが手掛けるそうです。  こちらが、玉の芯となる部分。深海産業で取り扱っている緑化資材の余りを巻いて作っています。これ自体も天然素材なので、深海産業の箒はどれも環境にやさしいものばかりです。  職人さんが使ってる道具も、各自で使いやすいようにカスタマイズされています。 こちらは銅線を締めるのに使う道具ですが、本来は電気工事用に使うものなんだそう。手前が新品の状態で、奥がカスタマイズした状態です。奥は、黒い持ち手の部分を削って握りやすくしているのが分かりますね。  これも、元々はプラスドライバーでしたが、先を落として削り、自作したものだそうです。専用の道具を揃えるわけではなく、例えば100均で見つけてきて改造するなどして、自分たちで使いやすいものを作っています。これも、既成概念にとらわれない深海産業ならではですね。  「こういった作業用の道具とかにしても、製品にしてもそうなんですけど。もっといい方法があるんであれば、ちょっとずつでも、いいものにしていきたいです」と深海さん。常に前進し続ける姿勢に、感銘を受けました。  ちなみに、今回の工房見学中に、キッチンブラシの制作体験をさせていただきました。先ほどご紹介した道具を使って銅線を締めて、中に折り込む作業に挑戦します。ひと通り説明をしてもらったのですが、やはり見るとやるとでは大違い!  足を踏ん張って体重をかけながら銅線を締めるのですが、想像以上に力が必要です。途中で銅線が切れてしまうハプニングもありつつ(笑)、なんとか完成させることができました。ありがとうございました。 棕櫚製品を、未来に繋いで 最後に、今後の展望をお伺いしました。 「あんまり世界中でバンバン売りたいっていうよりかは、地元に昔からあったものを、まず地元に知ってもらって。それが徐々に日本全国で『いいものやね』って広まっていけば、いちばんいいかなと思っています」と深海さん。 「江戸時代から棕櫚の産業はあったんですけど、今、地元の子どもたちに棕櫚ってなにか聞いてもひとりも知らないんですよね。その現状をなんとかしたいです」と津村さんも語ってくれました。 最終的には、和歌山県といえば、梅、みかんだけじゃなくて、棕櫚製品もあるということを知ってもらいたいそうです。  「僕らはビルみたいな建物を建てることも、大きな橋を架けることもできないですけど。未来に棕櫚製品を残せたら、自分の人生ハッピーやったなと思います。それをみんなでやっていきたいです。伝えていく自信はあるんで」 そう力強く語る深海さんをはじめ、スタッフの全員の背中には、「CRAFT WITH PRIDE(クラフト ウィズ プライド)」の文字が。 誇りをもって取り組む深海産業のみなさんなら、きっとその未来を実現できるはずです。  深海産業さんのものづくりでは国内の素材に固執することなく、作り方についても柔軟で、取り組み姿勢や環境も他とは少し違った印象をうけます。 考えられていることは「より質の良いものをより作りやすく」、そして何より「箒作りが次代にも続けられる産業になること」。 伝統に縛られて変われないものづくりはいずれ消えてしまう。これは多くの作り手さんの取材にうかがって感じていることです。「唯一、生き残るのは変化できる者である」ということですね。 積み重ねてきたものを変えるのは勇気がいりますが、その点深海産業さんはフラットな気持ちで取り組めたのが良いものを生み出せたのだと思います。 伝統を守るのではなく、大切にし、その芯の部分を理解すれば、それ以外の部分を変えることは日本ものづくりにとって今求められていることだと感じました。  深海さん、津村さん、深海産業のみなさま、長時間にわたる取材にご協力いただき、ありがとうございました! |
|

Broom Craftの商品一覧

国産棕櫚箒 | トレシア
|

国産シダ箒
|

国産棕櫚の万能ブラシ | トレシア
|

国産棕櫚の万能ブラシ
|

国産棕櫚・シダの手箒
|

国産棕櫚の鍋敷き
|
サイフク(mino・226)

|
|

|
|
雪国の冬に使われてきた「蓑」をモチーフにして生まれたブランド。 新潟の美しい四季を背景に、シンプルなデザインのニットアイテムを提案。 時代や流行に左右されず、長く愛用できる物づくりを心がけています。 |
|

|
|

|
|
「226」(つつむ)は、ヒトと暮らしをニットでつつんで、心地よくユーモアあふれる毎日へ導くことをコンセプトとしたブランドです。頭・手足・お腹など大事なカラダの一部から、インテリアなど生活を彩るプロダクトまで、すべて物を、楽しい工夫でつつみます。 |
|

サイフク(mino・226)取材記
|
|
ニットといえば、秋冬に着るセーターやカーディガンを思い浮かべる人が多いと思います。でも実はニットって、“防寒着”としての良さだけではなく、さまざまな魅力を持った素材なんです。 今回は、そんなニットの可能性を積極的に発信し続ける、ニット専門メーカー「サイフク」さんにお邪魔しました。訪れたのは、新潟県の五泉(ごせん)市です。  五泉市は、『ニットの産地』としてアパレル業界で広く知られた存在です。サイフクは、この地で1963年から物づくりを続けてきました。  お話をお伺いしたのは、常務取締役でブランドマネージャーの斉藤佳奈子さん(左)と、スタッフの 山木紗百合さん(右)です。 サイフクでは、2つのオリジナルブランドを手掛けています。   新潟の四季を生かして、シンプルなデザインで展開する「mino(みの)」。   体の一部からインテリアまで、いろいろなものをニットで包むことをコンセプトにした「226(つつむ)」。 それぞれのブランドの魅力から、知られざるニット作りの裏側まで、いろいろなお話をお伺いしてきました。この取材記を通して、みなさんのニットに対する意識が少しでも変化してくれれば嬉しいです。 時代とともに移り変わる、ニット業界 五泉市は、古くから豊富な水資源に恵まれ、繊維の町として発展してきました。着物から洋服へと時代の流れが変化するなか、五泉市も織物からニット製造へ転換していきます。 クオリティの高い商品や品質の安定性が評価され、今では、有名ブランドやデザイナーからも支持される『ニットの産地』として注目されるように。  そんな五泉市ですが、メーカー数は時代の情勢とともに、減ってきているそう。 「物作りが、日本から中国などの海外に移行したときがあって。そのタイミングでだいぶ減りましたね。価格と量の問題もあるので…」と斉藤さん。 自社ブランド誕生のきっかけ 自社ブランドを手掛ける前のサイフクは、アパレル業者から受注して商品を製造する、いわゆるOEM生産を行っていました。しかし時代の変遷とともに、それだけだと、ニットメーカーとして一年間やっていくのが難しくなったそうです。  一年の中でもだんだん“谷間”が多くなってきたころ、斉藤さんたちは立ち上がります。 「OEMの営業活動を頑張っても、なかなか谷間を埋められない状況でした。やっぱり『自分たちで作って、自分たちで売る』っていうことを早めに始めて、種まきした方がいいんじゃないかという話になり、自社ブランドの制作に向けて動き出したんです」 シンプルな作りの「mino」に込めた想い 最初に立ち上げたブランドが、2012年に誕生した「mino」。これはどのような経緯で作られたのでしょうか。 「アパレル業者さんと常にやり取りをしていると、すぐにセールがやってくるんですよ。『私たちは、すごく賞味期限が短いものを作っているんだな。生鮮食品みたい…』と思うことがあって。自社ブランドでは、あんまりそういうことをしたくないなぁと思ったんです」  「それに、今でもOEMでたくさんのアパレル業者さんと取り引きをしているので、そこを邪魔するようなものは、作りたくなかったんですよね」と斉藤さん。 確かに「mino」は、あまり見かけないシンプルな作りで、サイズ展開もなく、流行に左右されにくい。これは、そういった考えをもとに生まれたものなんですね。 外部と協力して、より良いものに 「mino」を立ち上げる際、一緒にブランディングに携わったのが中川政七商店さんです。こういった外部の方と一緒に動くことで、サイフクとしてはどのような影響を受けたのでしょうか。 「minoって、うちの商品の中で、もっとも簡単、もっとも単純な作りなんですね。ここまで単純なもので勝負するって、自分たちだけでやったら、なかなか踏み切れないと思います」と斉藤さん。  シンプル過ぎて「これで本当にいいのかな?」と不安になってしまうところを、「これでいこう!」と力強く背中を押してくれる。こういう部分は、客観的に見てくれる外部の協力があってこそ。 また、「mino」には、丸めて持ち運べるように紐が付属しているのですが、これも中川さんと話すなかで生まれたもの。お客様だけでなく、店頭で売るときにも便利なんだそう。 「中川さんは売り場を持っていらっしゃるので、店頭で実際に売っている側からの話を聞きながら作れたのは、とても良かったですね」 外部のチカラも、自分たちの糧にして ずっとOEMを中心としてやってきたサイフクでは、「企画をする」「作った後に売る」ということが初めてで、まさにチャレンジでした。その分、いろいろ苦労もあったのでは? 「なにかをやると、常に壁にぶつかるんでね(笑)。その時に『どうしよう!?』ってなっても、なんとか乗り越える。またなにかをすると、壁にぶつかる。もう、その繰り返しですよ(笑)。その繰り返しが、大変ではあったけど、今のノウハウや体力みたいなものにつながっていると思います」と笑顔で話してくれた斉藤さん。  「良いものを作っているから売れるはずって、作り手は思いがちですけどね。やっぱりそれを“伝える力”がないと。良いものを作って、ただ東京に並べてきました、みたいな感じだとお客様には分かってもらえないと思います」 そういう点でも、しっかりとした流通を全国に持っている中川さんと組みたいと思ったそうです。 「ブランドのスタートとしてはよかったんですけど、ただそれだけではダメなんです。もっとほかに卸す流通先をみつけるために、展示会に出るとか、ECサイトを立ち上げるとか。ひとつひとつやっていった感じです」と、力強く語ってくれた斉藤さんと山木さん。  私も、自社ブランドを立ち上げて頑張っているメーカーさんのところによく取材にいくのですが、「自分たちでちゃんと考えて発信していこう!」と動ける人が社内にいるかいないかで、そのブランドがうまくいくかどうか、変わってくると思います。「外部の人と一緒にやるから、全部おまかせすればいいんだ」というスタンスだと、たぶん難しい。ブランドを作るって、そんな簡単なことじゃないんです。自分たちでやるっていう、意識があることが大事なんです。 「外部の方も、永遠に並走してくれるわけじゃないですし。ひとり立ちしてやっていくには、自分たちがチカラをつけていくしかないですね」 ニットのおもしろさを発信する「226」 では、2つ目のブランド「226」が誕生したのは、どのような経緯があるのでしょうか。 「minoを立ち上げてしばらくやっているうちに、minoだけでは、ニットのおもしろさが伝えきれないなぁと感じるようになったんです」と斉藤さん。 「mino」には、シンプルな作りの良さがある。でもそれとは逆に、いろいろな編み方ができたり、伸び縮みしたり。そういう部分もまた、ニットの魅力のひとつ。ただ、その部分を「mino」に入れてしまうと、ブランドの世界観が崩れてしまいます。  「もっとニットの可能性みたいなものを表現できるブランドがほしい、と思って作ったのが226です。どちらかというと総合ブランド的な感じで、衣料だけじゃなくて、バッグとかインテリアとか、なんでもやっています」  「226」はロゴのデザインもユニーク。「226」の下にある「3129」はサイフクの社名、「5000」は五泉市の五泉。よく見ると「210」のニットも隠れています。 「もっと自分たちを前に出したブランドにしたいっていう、想いも込めています」 ブランドを起点に、広がる輪 「226」を立ち上げてから、意外とOEM生産の方にもいい影響があったそうです。 「例えば、今までOEMではバッグみたいなものって作ってなかったんですけど、226にバッグがあることによって、ここから派生して、コラボのお誘いがきたり。イスメーカーさんとか、普段なかなか出合わないようなメーカーさんとつながれたり」  「226」でいろんなことをやっているからこそ、さまざまな企業からお声が掛かるようになったとか。発想次第でいろいろ作れる、ブランドならではの魅力がよい結果に広がっていますね。 社内の人間だから、できること ブランドマネージャーでもある斉藤さんは、商品のデザインも行っています。しかし、もともとデザインの経験がなかったというから驚きです。 「最初は外部のデザイナーさんにアイディアをもらったほうがいいのかなと思ったりしたんですけど…。結局はニットのことをよく分かっていて、うちの機械背景の特長をうまく生かすことが大事だったりするので。自分でうんうん悩んだほうが、スジのいいものが出る気がして」  特にそれがよく分かる商品が、226の「見せるハラマキ」シリーズ。お腹の部分が薄くてすごく伸びる生地なのに対し、裾部分は見えても下着っぽくないよう、しっかりと厚い生地に。 「こういうデザインも、それぞれの生地を縫製してくっつけるんじゃなくて、このまま編める機械がうちにはあるんですよ。そもそもこの機械は、薄手のセーターのケーブル模様だけ厚く表現したいっていうときなんかに使ったりするんですけど。この機械のおもしろさって、なにかに使えないかなとずっと思っていたんです」 機械の特長をきちんとつかみながら、一般消費者の「腹巻は使いたいけど、腹巻として見えるのはイヤ」という心理具合も見事に汲み取った商品。これは、外部のデザイナーさんではなかなか出せないものですね。 知っているようで知らない、ニットの製造現場 さて、ここからは、実際にニットが生み出される現場にお邪魔してみましょう。  最初は、糸を編んで編地を作る工程です。こちらはパソコンで、編地を編むためのデータを作っているところ。柄を組むのはもちろん、糸を何本で編むのか、ふわっと編むのか、ぎゅっと編むのかなど、いろいろなことを何度もチェックしながら作っていきます。   先ほど組んだデータをもとに、こちらの大きな編み機で編んでいきます。サイフクには、なんと80台もの編み機があるそう! 「編み機は同じように見えても、それぞれ針の太さが違うんです。針の部分をごそっと取りかえればほかの太さが編める…というわけではなく、ひとつひとつがその太さ専用の機械なんです」 それで、こんなにたくさんの編み機が必要なんですね。  こちらは最新のホールガーメント機。縫い目のない、無縫製の商品が編めるそう。  ここは洗いの工程を行います。大きな洗濯機と乾燥機のような機械で、水洗いやお湯洗いなどをして、風合いよく仕上げていきます。  編み機で編んだ編地を、パターンに合わせて裁断していきます。前見頃、後ろ見頃、袖、ポケット、フードなど、それぞれのパーツごとにどんどん分けていきます。  こちらは縫製の工程です。ミシンやロックミシンを使って、スピーディに、立体的に縫っていきます。  普通の生地と違って、ニットを縫うのは難しそうですね。 「ニットは伸びたり縮んだりするので、縫うときはちょっと縮めながら縫って、伸びすぎないようにしています」と職人さん。  こちらは「リンキング」と呼ばれる縫い合わせの工程です。編地のひと目ひと目を、もう一度針に刺していく、非常に細かい作業! 職人さんの手元を見ていると、思わず息をするのも忘れてしまいそう。  リンキングではループとループを同じ針に刺して縫い合わせるので、縫い代のない仕上がりに。襟元など、伸び縮みの必要な部分によく使われます。  こちらは仕上げの工程。縫っていると端に糸が出たりする場合があるので、それをきれいに取りのぞいたり、キズがあれば直したりしています。  蒸気が出る台の上に置き、縫ったあとの縫いジワを整えていく工程です。金枠にセットして、指示通りの寸法を出していきます。  最終の検品をして出荷します。襟ネームや下げ札がつき、私たちがお店でよく見る商品に。 今回はざっと駆け足で見学させてもらったのですが、商品だけ見ていると気付かないところや、作られるまでの大変さを知ることができました。リンキングなど初めて見る作業も多く、これからニットを着るときに、思わず襟元を確認してしまいそうです(笑)。 これからも、ニットの魅力を形に 最後に、これから先、めざすところについてお伺いしました。 「いろいろ作っていくなかで、やっぱりもっと気軽に洗えるようにしたいなと思っています。ニットの衣類を洗濯機で洗えるようにするには、糸や作りなど、けっこう考えないといけなくて…」と斉藤さん。 「ブランドでいえば、minoと226のブランドの差が、なくなってきちゃった部分が最近あるので。minoはもともとある、新潟の四季というコンセプトに立ち戻るようにしたいなぁと思っています」  常に自分たちで考え、生み出していくサイフクさん。今後の課題もきっと乗り越えて、新しく、楽しいアイテムを、また私たちに届けてくれることでしょう。 長い時間、取材にご協力いただきありがとうございました。 |
|

minoの商品一覧

洗えるストールポンチョ nico
|

透けるボーダー ストールポンチョ nico | 涼しい麻
|
226の商品一覧

見せるウールハラマキ
|

のびるニットロングスカート
|